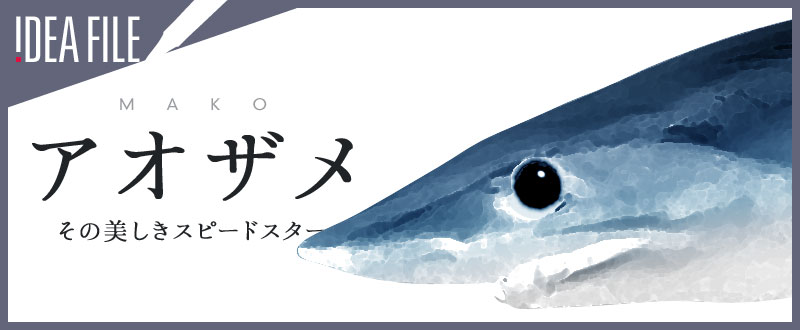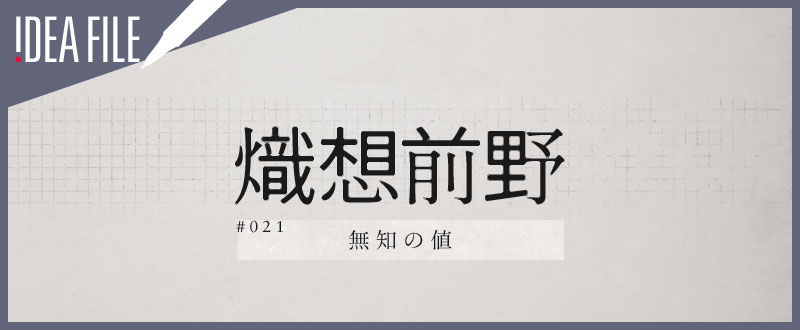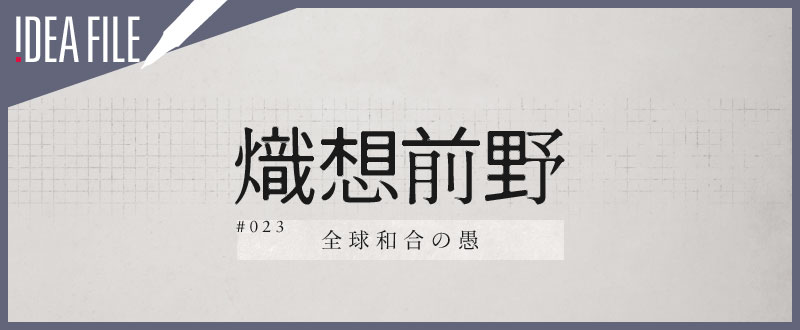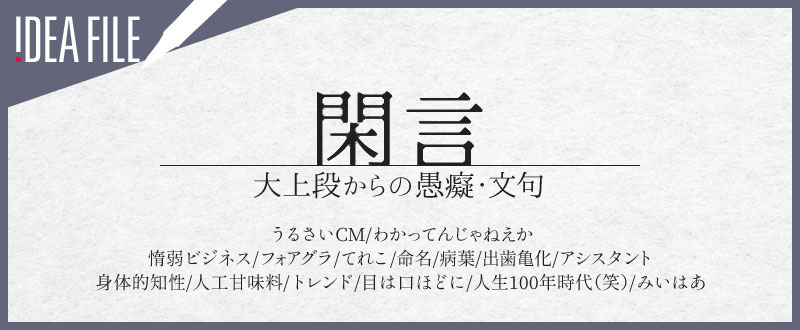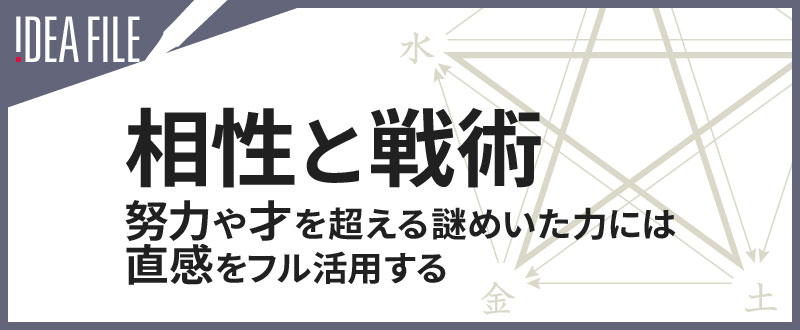知の嗜み
統合的知性と傲慢な知性
運動を止めた「知」は「準死知」にすぎない。それは時にドグマであり、カルトであり、イデオロギーであり、知を騙るもの、知に似て非なる神経症のようなものである。
知の統合
上から見ると「丸(視座a)」、横から見ると「三角(視座b)」、正面から見ると「四角(視座c)」というかたちをここでは「実相(真実のすがた)」と仮定しよう。
たとえば、実相を「丸」と解釈する「視座a」にあるものは、「三角」と解釈する「視座b」にあるものを次のように誹り、「実相」を見誤る。
おのれの解釈(丸)に他の解釈(三角)を閉じ込める(include)のである。そしておのれの解釈(丸)が他の解釈(三角)よりもより統合された、補完された視座であるという。しかし、その解釈ではおのれの解釈(丸)は「丸」のまま、新たな視座と認識を得ることはなく、つまり「実相」に達することはない。
「誹謗」とは「丸」にたいする「三角」の不足領域を誹るさまだ。が、そも「三角」が不足領域をもつのは、三角が丸の内にあるとする恣意的で傲慢な前提であるから、無明性がある。これはドグマ★1によくみられる。
カルト★2、イデオロギー★3も同様、なべて「実相」の探求、漸近よりも、おのれの類型の拡大と強化、優越性の誇示に腐心する。イデア★4の流失、ロゴス★5への昏迷――実相など何処吹く風――そうした態度を決め込むものを「知の嗜みを知らぬ」という。
要諦のひとつは「無知の知」だ。「おのれの知っていることなど常に宇宙の1%未満にすぎない」という、謙虚さといってもよい、「知不足」が知に「活」をもたらす。するとどうなるか。
おのれの解釈(丸)の無知領域が仮構され、拡張の動態をとる。これが「活」状態であり、結果として「丸」に加え、一理あるという認識とともに「三角」の視座も得る。「実相」に一歩、近づくこととなる。これは中立的批判・批評である。
同様にしていずれの視座からも「実相」への漸近は等しく可能だ(八万四千の法門
とはこういうことをいうのだろうか)。
世間は、やれ右だ左だ、保守だリベラルだとやっているが、「統合せよ」という自然の数の大号令、あるいはニューロン★6の囁きが、声高に過ぎる自らの声でかき消され、聞こえないようだ。
概して批判と誹謗の区別もつかないのは、こうした知の運動性の側面を観ないからだ。知は運動であり、エネルギーである。
硬直した知は一見、知性のように見えるも、その実、運動を止めた準死知にすぎない。ドグマ、カルト、イデオロギーの類がそれだ。統合の労をきらう知性は、知に似て非なる神経症のようなものである。
★1 ドグマ(dogma)――教義、教条。独断、独断的な説・意見。
★2 カルト(cult)――狂信的崇拝。少数の人々の熱狂的支持。
★3 イデオロギー(ideologie)――一般に、政治的・社会的なものの考え方。思想の傾向。
★4 イデア(idea)――価値判断の基準となる不変の価値。
★5 ロゴス(logos)――ことばによって表される理性、宇宙の理法。
★6 ニューロン(neuron)――神経細胞。
因縁的先入見
知には厄介なことがある。それは個人のおかれた時代や国や地域といった技術的・文化的環境、社会的・経済的環境、生理的・心理的状態、経験的事実の解釈における差異性、そして超人知的な潜在的要素が複雑に連関し、もちうる視座は必然的、運命的、そして無運動的だということだ。視座とは、知的な自由運動の末の主体の発揮などではけっしてない。
人はみな、「因縁的先入見」という無限の知点のひとつに鋼の錨をおろし、そこに無運動的知を、必然的、運命的生を据える。
縦横無尽に飛翔する視座をもち、実際的に「実相」をつかむことは人間風情には不可能である。であれば想像による実相への漸近の試み、統合の試みが「知の嗜み」ということになる。
人は想像力によって因縁のしがらみから浮揚することならできる。別言すれば、知的にのみ実相にたどり着いた地動説、そこには天動説に比して「知の嗜み」があったということだ。
実相への漸近の試みは、学術的手法のみが可能にすると妄信すれば、エリート知性主義的なドグマに陥る。宗教的手法のみが可能にすると盲信すれば、カルトに陥る。歴史的・社会的に規定された手法のみが可能にすると猛進すれば、イデオロギーに陥る。
ついでにいうと、技術的手法のみに傾いたものがテクノロジズムである。技術、もとい今でいえばAIが因縁的先入見から解放された全球的な視座を獲得し実相をとらえるとの見方は浅見にすぎない。AIの出力もまた総集的かつ入力という先入見を祖とする。試しに「塩 身体に良い」、「塩 身体に悪い」と個別にAIに訊くと、その解答の内容は同じだ。これは共に先入見として入力されている論理の両立を計った、ある種の詭弁であり、カントがいった理性のみで全体的な問題を解決しようとすると二律背反に陥る
「アンチノミー(antinomy)」であり、実相への漸近の運動ではない。
想像の運動(無知の知の想像)をやめたとき、知は単次元的現実(状況)のイナーシャに呑まれる。そして理非も実相も其方退けで、固定点の風見鶏と化し、準死知としての天動説(流行、趨勢)に執われるのである。
知の嗜み
本源的には、知的にしか進歩の伸びしろがないのが人という生命であろう、物的には生老病死を免れない存在だ。それがもはや知的な進歩を望めなくなったとき、技術が知性にとって代わる。それが技術主義であり、技術主義とは虚無主義の派生である。進歩といえば火星への移住やAI騒ぎにみるような技術的拡大のイメージしか描けないというのは、枯渇した本源性、虚無を技術に投影しているにすぎない。
当今、人の知は頽化している。それは「よく生きる」から「ただ生きる」へ、生の質の変化、位相の変化として表れている。
知が頽化、低次化したからこそ――野蛮が適正手続(デュー・プロセス・オブ・ロー、due process of law)を優越する。たとえば、おのれやおのれの家族には使用しないような治療法で利益の拡大を図るように。たとえば、人身売買や集団殺戮が利益効率の名の下に商法化されるように。たとえば、精神や文化までもがスクラップ・アンド・ビルド(scrap and build)の対象となり、人間不在の市場原理が標準化されるように。
ドグマとしてしか機能しない権威、宗教法人でなくともカルト、誹議と気受けにしかカロリーを消費しないイデオロギー、――知の腐敗――。
「知の嗜み」の実践、まずはありのままを――見詰める――耳を傾ける――。そこではなにも結論せず、ただ観照する。いつか必要な時に、想像の次元でそれらの事物を観取するときがくるだろう。寂然と沈黙の高度に精神がさしかかるとき、自然にあきらかになる、事物の空しさと意味とが。そうして精神の俎上ではじめて、事物は真的に運動する。内なるものとして、知が、生がようやく生きる。
人における実相の認識、統合の総観は、人である以上かならずや精神の次元にあらわれる。秩序も実相も、技術の上ではなく精神に生じる(in-spire)ものである。
外界にはただ見詰めるべき偶像が、耳を傾けるべき騒音が、塵と風紋からなる茫漠たる沙漠があるのみだ。知の焦点距離が近視眼的に固まってしまえば、「沙漠の空しさ」という宇宙の段階的真実をありありと、永久的に観ることになる。それは自虐的に過ぎる。安物でもいいから眼鏡を、もとい拙速でも「知の嗜み」の実践を。
俗世界隈のみたいな「知の窘み(困窮)」ではなく「知の嗜み」を。