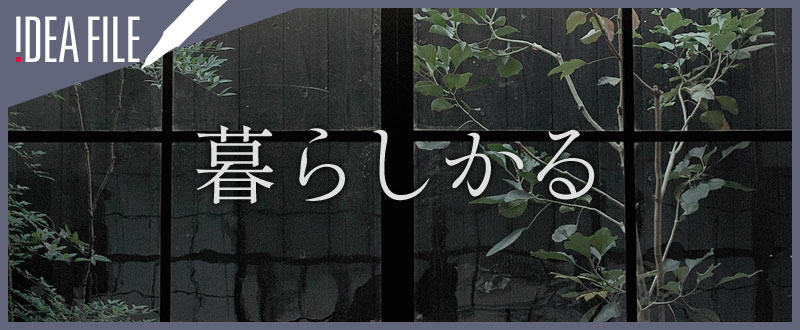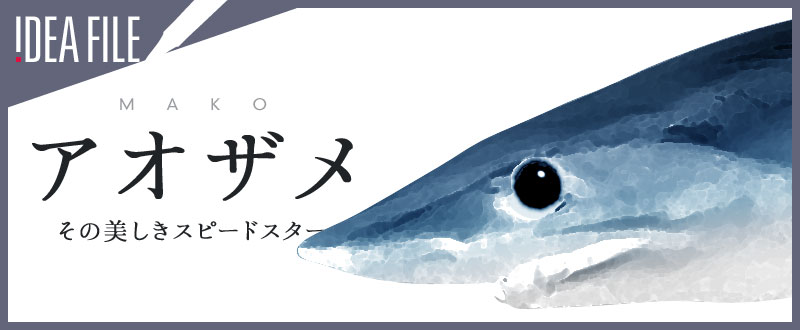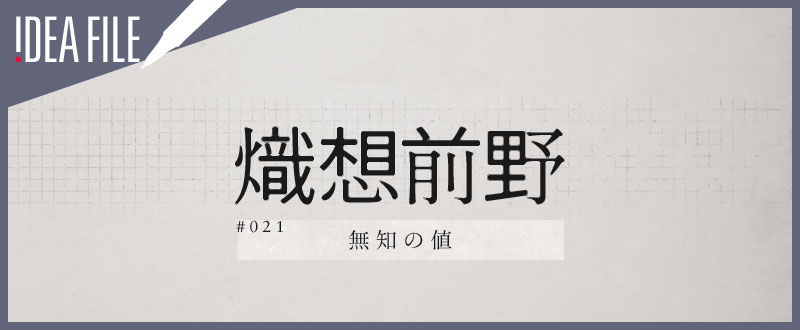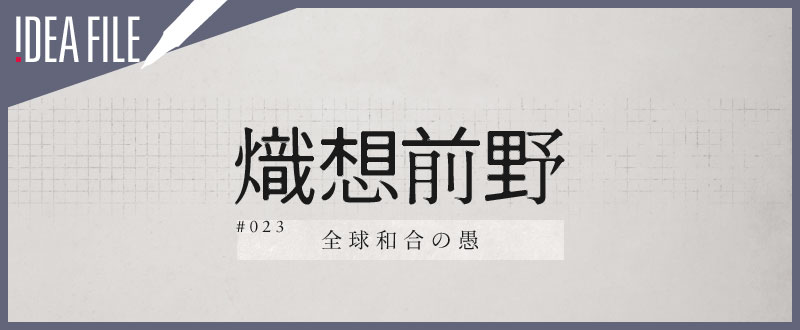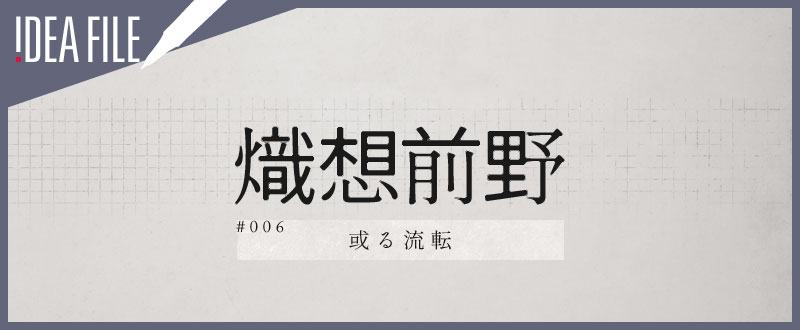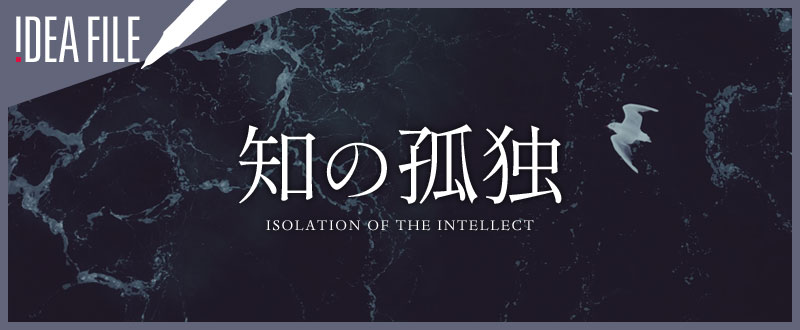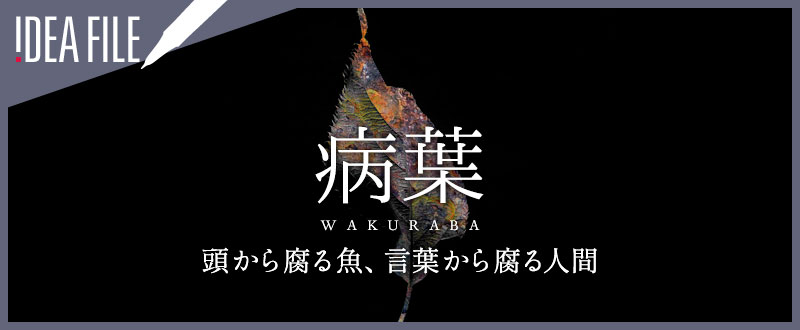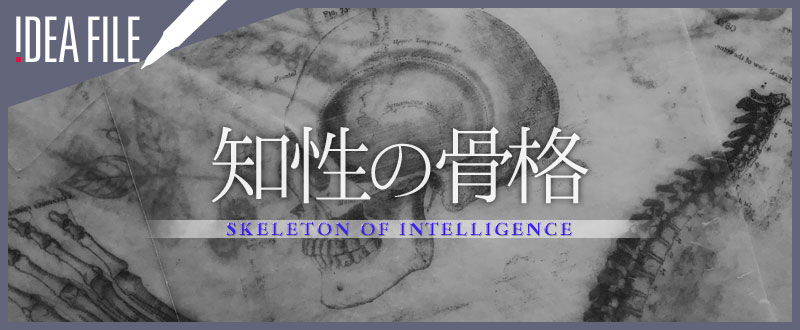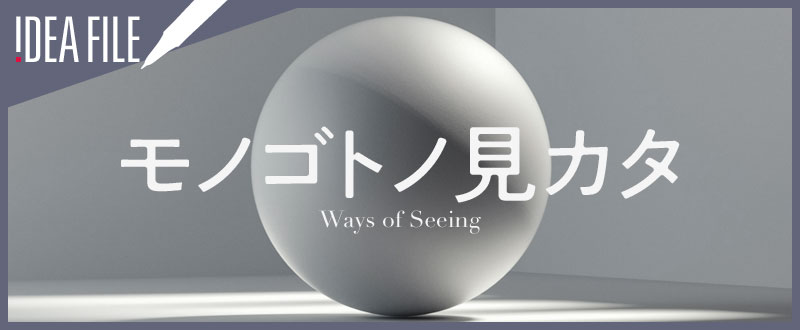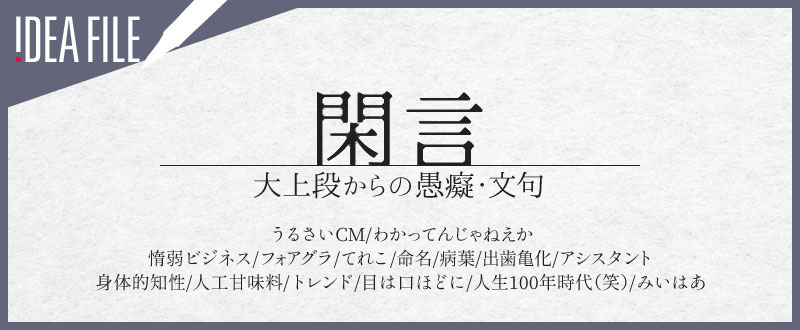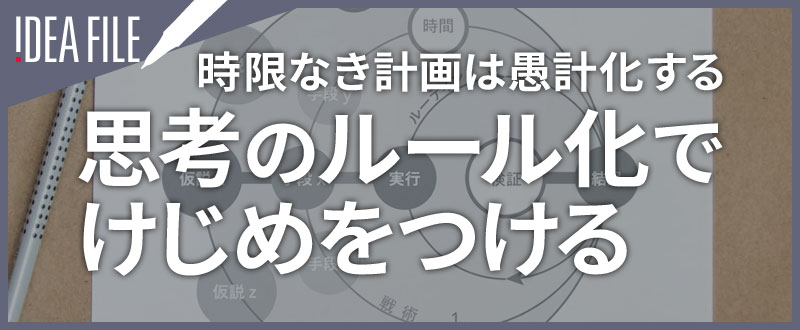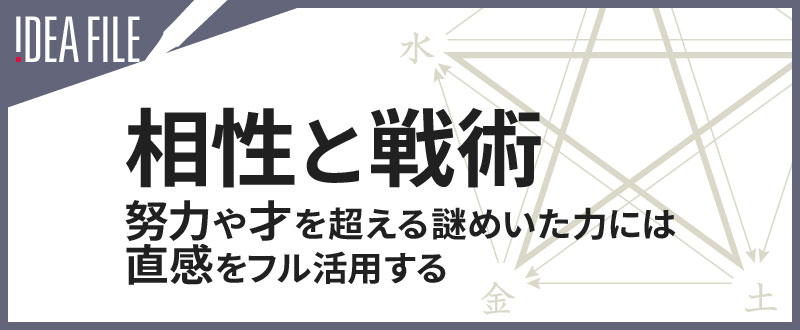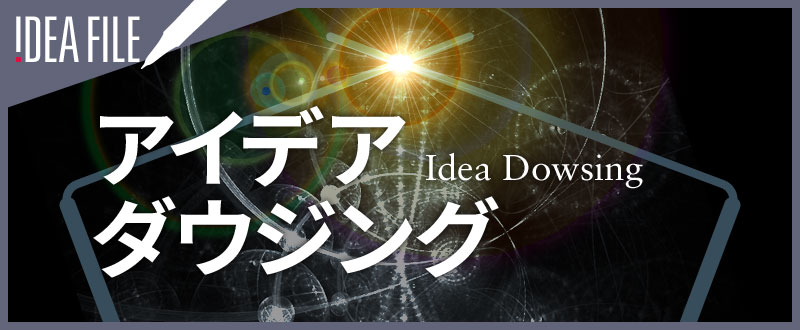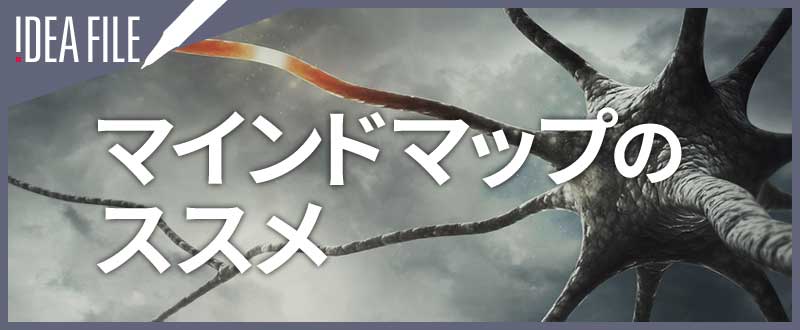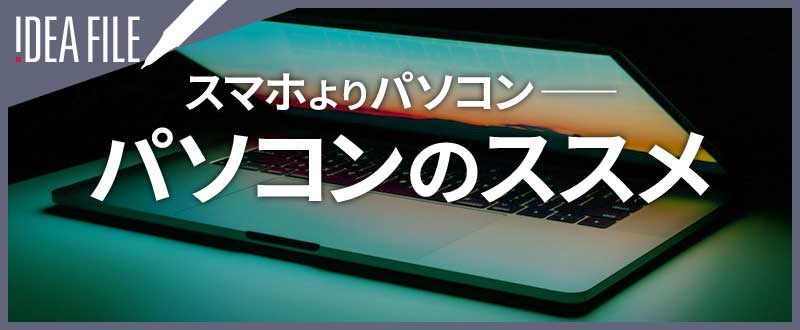靜心
経験から解釈へ 外化と内化の旅路
凡庶は経験に学び、知者は解釈に学ぶ――
牛飲水成乳、蛇飲水成毒
、水が乳と毒という反意的な二つのものに分かれる、その転轍機は〈解釈〉にある。外化と内化の旅路を論じる。
靜心
太平洋側の地域は陽射しのとどくところが多く、お出かけ日和となるでしょう――。
お出かけ日和、けっこう。たしかに、澄みわたる碧空は刺激的だ。あの空をみすみす室内でやりすごすことは、なにかもったいない気がする。が、だからといって、いい大人が日和の次第で、こせこせするのもどうか。
余生は観光地なる場は不用――。
そういう場に蝟集する人々を見ては「こうも旅行にやっきになる、ほんとうに情意から欲したことなのかね」と思う。「オーバーツーリズム(観光公害)」という言葉もあるが、イナゴの大群よろしく、メディアの暗示にかかった反応にもみえる。トレンドと化した旅行は、たしかに「ツーリズム(tourism)」だ。イズム(ism、主義)であって、型にはまった態度、しみじみとした風情は感じられない。
次の休みは、どこ行こう――。
見慣れた感のある惹句だが、週一杯働いて、ようやくたどり着いた余暇は軒並、外に出る。落ち着いて座学に浸る暇などないだろう。「そんなものは学生時代で務めを果たし終えた」とでもいうだろうか。そんなものは学業成績というその時分のスコアアタック★1にすぎない。人の知分に定められた卒業などない。
「座学」といえば講義形式を思い浮かべるかもしれないが、ここでいう「座学」は、独り、しみじみと思い考える状態、「靜心(しずごころ)」のことをいう。観光地で映える★2物や風景について考えることでは、断じてない。
★1 スコアアタック――獲得したスコアを競うこと。ゲームの競争形式のひとつ。
★2 映(ば)える――主にSNSで目立つ、目を引く写真のこと。
凡庶は経験に学び、
知者は解釈に学ぶ
愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ
とはビスマルクの言葉だが、捩って、凡庶は経験に学び、知者は解釈に学ぶとする。
自ら博雅の士を気取る彼はいう、「何せ、世界〇か国、実際に行って、見てきたからね」と。ただ、彼の話はどうにも浅薄で、つまらない。彼が蓄えた一切は知見ではなく、マイル★3なのではないかと疑うほどに、つまらない。稚児の日記のように、どこそこでこんなスゴいものを見た、ヤバかった、ウマかったマズかった云々……。
やはり、と確認するにいたる。そう、凡庶は経験に学び、知者は解釈に学ぶのだ。数多の渡航経験は、彼に散文的な経験をもたらしはした。しかし――散文的にたいしては詩的といいたいところだが――靜なるものは涵養しなかったようだ。静思、静修、静慮――。
宇宙の理を知悉するには、宇宙中をくまなく踏破せねばならない――というのが凡庶の発想なら、花一輪に宇宙は看取しうる――というのが知者の発想だろう。それは「静観」である。
彼は人より多くの空間を経験したということから一日の長を自負しているが、その言葉を観るに、何のことはない、凡庶である。
同じような日々であっても――同じ道を歩き、同じ電車に乗り、同じ立居振舞の繰返しでも――人は満たされることができる、解釈によって。
牛飲水成乳、蛇飲水成毒
とは「牛の飲む水は乳に、蛇の飲む水は毒になる」という意味だ。水が乳と毒という反意的な二つのものに分かれる、その転轍機は解釈にある。
すべての事象は本質的には中性的(neuter)だ。換言すれば、極性も極間も含み併せもつ総合性だ。揺蕩う総合性の大海から、人が一杯を汲み取り、ウマいだのマズいだの解釈したとき、意味や価値が生じる。ひいては乳と毒のごとき効果が生じる。解釈即効果なのだ。
同じ道、同じ電車、同じ立居振舞の繰返しを「オモシロくない」と解釈したとき、負価値が生じ、伴ってストレス性の神経伝達物質(毒)が生じる。そして、「次の休みは、どこ行こう」となるのだ。解釈次第で眼前の吊革が映えるアートになりうるというのに、ことさらに有限の時間と、ついでにカネを費やして、こせこせと「ツーリズム」に参加するのである。
★3 マイル――航空会社独自の対象サービスを利用することで貯まるポイント
外化人
経験にことさら価値をみるもの、経験にことさら貧富をみるものは、イモムシのように経験を蚕食することに励みがちだ。それは「外化」された次元にのみ、新たな、快楽的な、価値のある認知の素材があるのだと信ずる、ある種の唯物的経験主義者である。彼らはリソースを間断なく外化の次元に投資する。外的構造のサーフィンを畢生の目的とする彼らに、実際、ツーリスト(観光者、旅行者)的人物を見受ける。彼らは一見、平和的だが、その性質は大航海時代のアングロサクソンのような貪婪さという点で通底している。それは蛮性に裏打された拡大志向である。
時間、空間、情報、流行、欲望等……外化人は、止まると死ぬマグロのように、外的資源を取り込みながらしか生きられない。すでに見たように、彼らの自存も自尊も、外的経験によってのみ支えられる。ゆえにコロナ禍のような外的世界の停頓状態は彼らにとって酸欠状態を引き起こす、存在の基礎をゆるがす問題となる。
また、その観念傾向から、人間の外性、つまり肉体の疲憊をことさらに恐れるジェロントフォビア(老化恐怖症)も見受ける。
これらの総観が「旅先で、映える、とうかれさわぎ、現地の景色を背にピース(Vサイン)」である。
当今、こうした外化人が、進取の気象に富んだ、活力ある人々と謳われる。が、その深奥は、活力のほぼすべてを外化しきった、内的には中空化した、無意識的虚無人であることもまた見受ける。以前、述べたように、あのピースの「V」は「vanish(消え失せる)」の無自覚的表明のようなものだ。自意識過剰に見えて、その実、真に自己なる意識は消え失せた、自意識過小な群衆人である。
彼らの活動次元(x,y)はきわめて空間的で表層的だ。ちなみに唯物的時空観の当世との相性がよく、カネの環流にはポジティブな効果を示す。ゆえに操作された態度、イズムめくのである。
そも、モダングローバリズムなるものは、モデル(ひな型)に向けて価値やインフラを収斂させる運動である。その思潮をひた走る世界にあって、とくに各国都市部の非差別化は顕著、ほぼ収束しているありさまだ。東京からソウルやパリ、ロンドンへ異国の風光をもとめて旅したところで、外界はほぼ同型である。否、その国ならではの文化財を観てまわるのだといったところで、ツーリズムという名のグローバリズム、群れ集う観光人により、やはり同景と化している。
どこも似たり寄ったり――その既視感に無意識的な焦燥を感じているからこそ、血眼になって「映えるもの探し」などという滑稽に嵌るのである。

そうまで挙って、観光せねば気が済まんものか?
内化人
「内化」は、別言すれば非行動的、非空間的ともいえる。実際、「外化」とはちがい対外性をもたず、たとえば経済的視点からは「不活発」と揶揄されかねない。それは、一理ある。ただ、過熱、過激化した外化から「オーバーツーリズム」という言葉も生れる昨今においては、冷や水として、また、拙論の価値の置き所として、「内化」を主旨とする。
「内化」は認知の拡大・深化等に、数量的な時間・空間を要しない。いわば非空間的な動態をとる。さながら思弁的であるがゆえに、「仮想」や「妄想」、「机上の空論」といった中空の活動のように揶揄されることもある。が、ある水準に達した解釈力をもつもののそれは、如何して、まごうかたなき実践である。
現象的には慣習的に繰り返す時空にあって、認知内容をより深みへと進める(z)、つまり「今此処の運動」である。静態にして、それは立体的(解釈性、修辞性、蓄積性等)運動だ。軸(z)は非空間的であるため無限性だが、その無限性の美的否定、意匠性をここでは「文化的なるもの」とよぶ。「文化的思考」、「文化人」はこれに属する。
「靜心」は文心(あやごころ)とでもいおうか。そこには内的表現の、節回しの技巧がある。日々の「同じ」に文心の微意を含める。シクロフスキーが提唱した異化にも通ずる、事物の芸術的再生、積極的な詩的解釈でもある。
炊けた米の香りが、いつになく美味そうに感じられる――。
ファイルの命名規則を変えたら、なんだか、恰好が付いた――。
あいにくの雨だが、裾上げがうまくできたから、お出かけだ――。
「七十二候」は、一年のうちに七十二もの季節を感じ、表したものだ。文心があれば如何様にも楽しめるし、価値を見出せる。なんなら水を飲まずとも乳を作りだす、人間の知にはそんなデザイン力があるのだ。知は力なり
である。
旅はいいものだ
旅は旅魂だ。行先は二の次、映えるかどうか、論外。
走る車の窓から身を乗り出さんばかりに、興味津々といった瞳の犬を見ては思う、その瑞々しい黒の目鼻をとおして、感じているものが「旅」なのだと。旅とは其処に在るものなのだと。卑近との距たりばかり意識していたら、マイルばかりかせいでいたら、旅魂は魂なき旅になってしまう。
何処の烏も黒い
とは、場所が変わったからといって、人や物事の本質は大して変わらないというたとえだ。
およそ旅魂など感じさせない、大発生し、大集団で移動する「レミング★4」は、漢字で書けば「旅鼠」だ。
よもや白い烏をお探しか? 観光という名の単なる(ネズミのごとき)大量行動に与してはいまいか?
旅魂、それは「靜心」という解釈の時空にある。
私にのみ通ずる垂線の路を、今日も私は旅する。
表相を渉猟したところで、行き当たるのは情報、情操は深相に出来する。
旅は、いいものだ。
そうまでせずとも。
★4 レミング――ネズミ科ハタネズミ亜科のうちレミング属・クビワレミング属などのネズミの総称。体長10~15センチメートルほど。