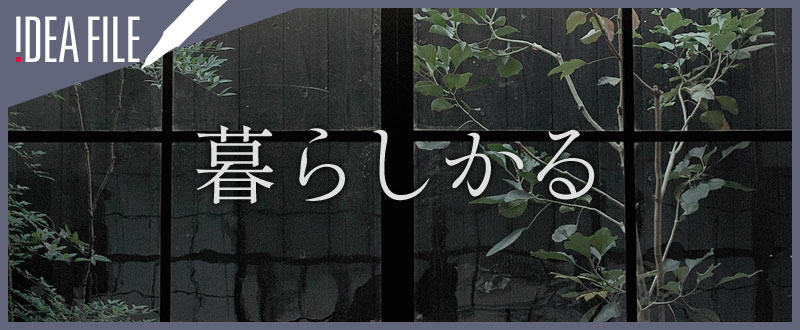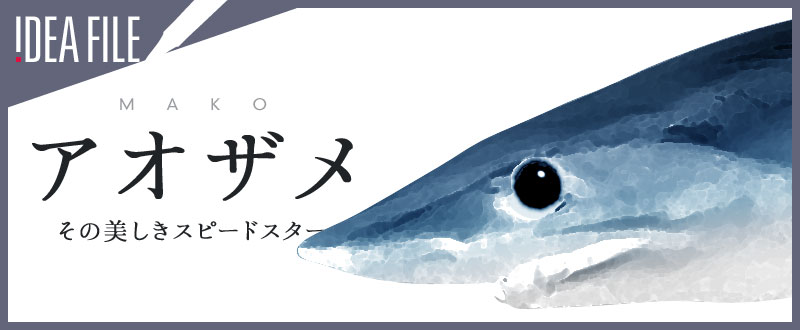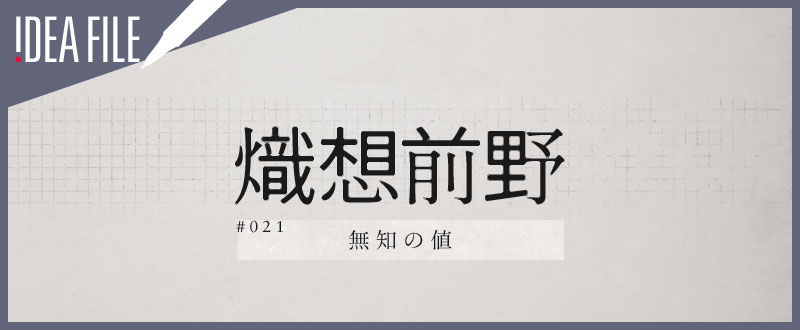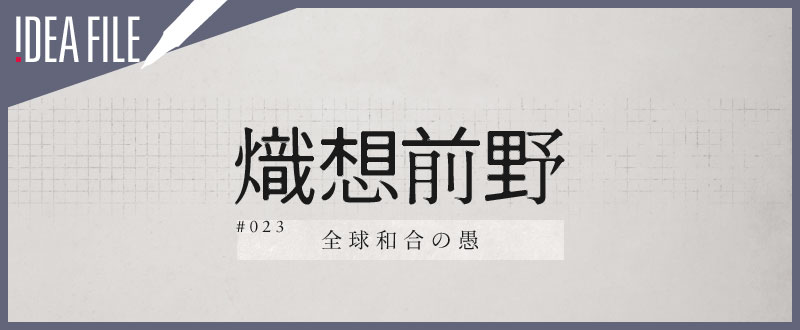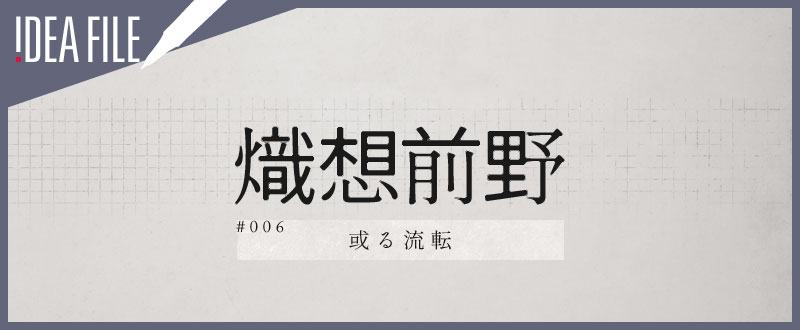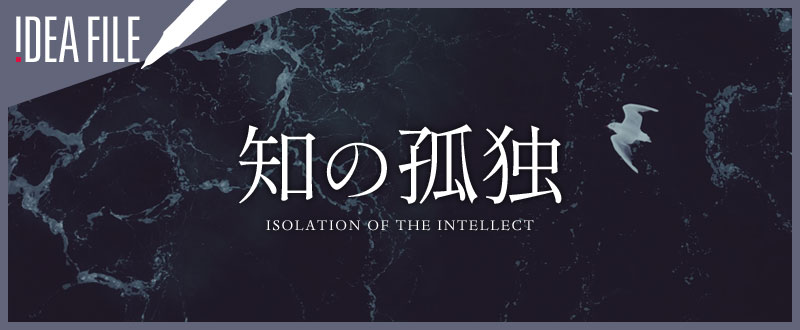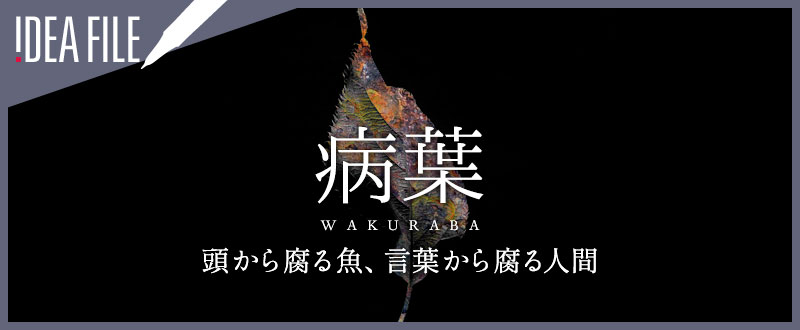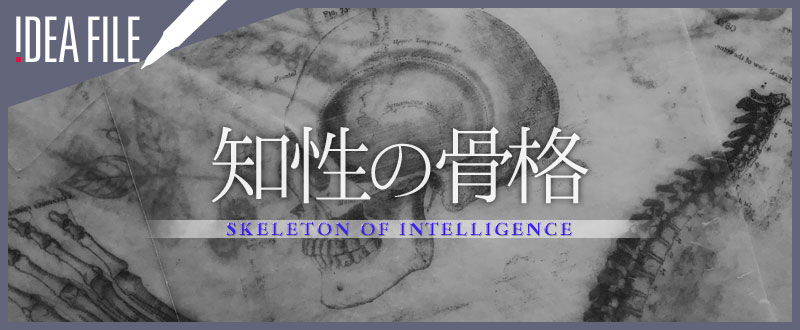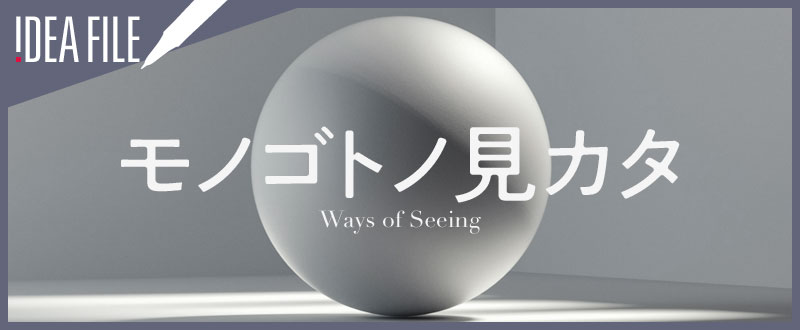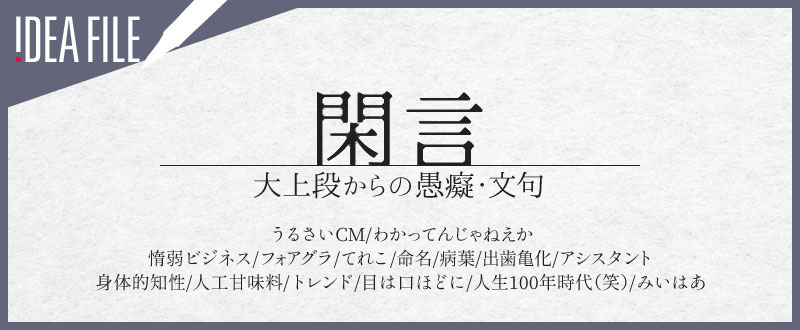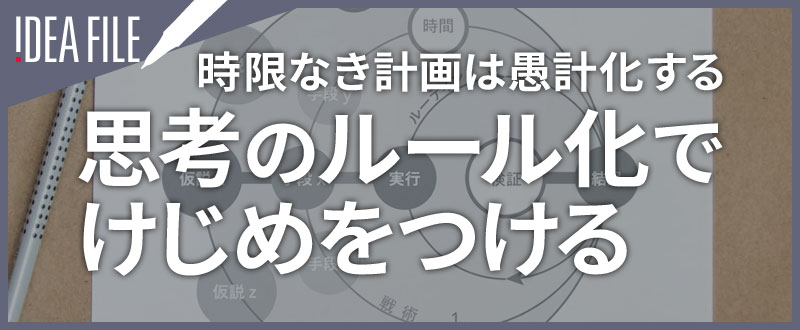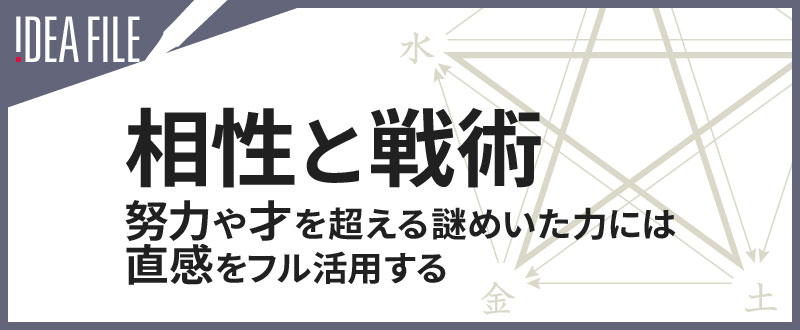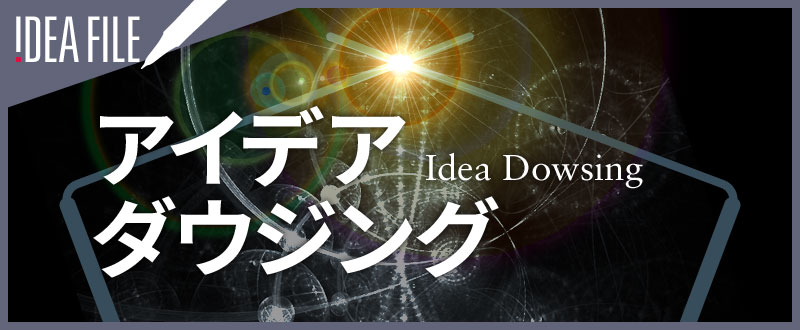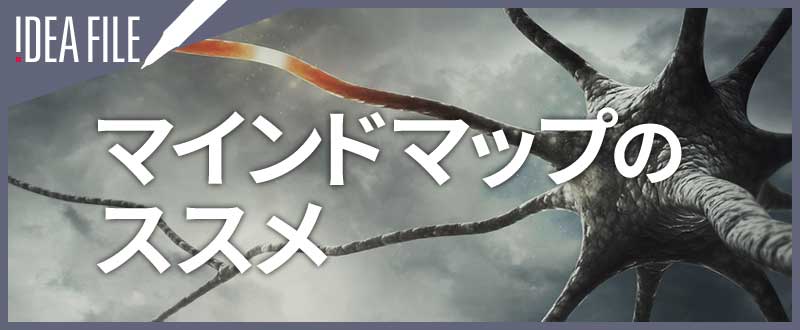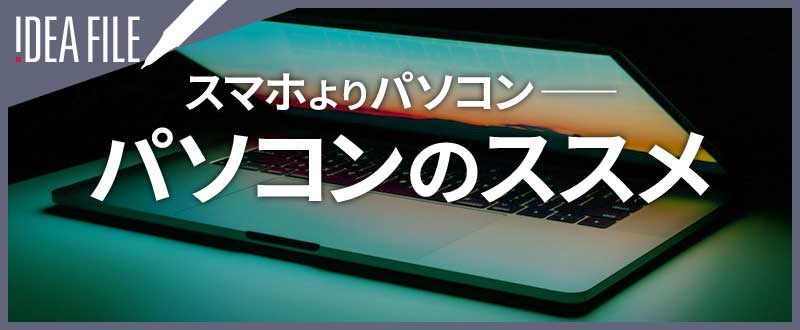機動戦士ガンダム
――それは現代の神話か
40年をこえて宇宙を翔びつづける機体だとは、当時、考えもしなかった。『機動戦士ガンダム』――私にもっとも影響したロボットアニメだ。「ガンダム」はなぜこうも人を魅了するのか。色褪せることのない「白いモビルスーツ」に、私は、人は、なにをみているのか。1979年の放映から半世紀のロングランを目指す今、『機動戦士ガンダム』を語ろう。
未来的神話
ここに一冊の古い本がある。『ワクワク・フィルム・アルバム〈6〉映画版 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙編(株)サンケイ出版、昭和五十七年四月二十七日発行 』。昭和57年といえば1982年、(現在2021年だから)39年前の本だ。私はこの『機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙』を劇場で観たような気がする。否、この39年前の本同様、壊残した記憶のくいちがいかもしれない。
いずれにせよ、子供だった私は第1作目の『機動戦士ガンダム』の「一年戦争」を無我夢中で心に焼きつけたことはたしかだ。今にして思えば、はじめて触れた「叙事詩」だったといえるかもしれない。
物語の背景となる「宇宙」や「スペースコロニー」は別世界、別次元的な世界として幻想的だった。巨大な「モビルスーツ」や「モビルアーマー」は超自然的存在に置換可能な存在だ。登場する人物はギリシア神話の男神・女神たちのような複雑な関係性のなかに生きいきと脈打っている。
それらが織りなす物語は、社会の意味・価値・規範、そこからの葛藤、歴史的事件、意思と感情の相克――。『機動戦士ガンダム』は『ベーオウルフ』や『ニーベルンゲンの歌』の類に似て叙事文学的であり、また神話的でもある。

『ワクワク・フィルム・アルバム〈6〉映画版 機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙編』©創通・サンライズ
『機動戦士ガンダム』という完成形
私にとってのシリーズ「ガンダム」の精髄は、やはり『機動戦士ガンダム』にある。「アムロ」といえば安室奈美恵ではなく「アムロ・レイ」と答えなければ、私の答案用紙では罰点だ(人みな時代の子たるを免れえないというジョーク)。
『機動戦士ガンダム』につながる作品『機動戦士ガンダム THE ORIGIN』。そこで描き直された「MS-06S(シャア専用ザク)」の美しさよ。40年をこえて型崩れしない同作品のデザインの骨格の強さをみる。
『機動戦士ガンダムUC』のクライマックスでは、遡る時の流れのなか、「機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙」の光景が現れる。壮大な叙事詩の記憶の感動がこみ上げる。
これらがたしかに40年前に描かれたものであることを再認識する時、あらためて、この作品の偉大さを再確認するのである。

「ディオラマワールド」の写真ページ。現在「3D化」といえば「CG化」へとはしるのが通例だが、当時は「ガンプラ」こそがガンダムの3D化だった。立体物として再現可能な高度なデザインとディテールだからこそ「ガンプラ」はアニメーションと並ぶコンテンツとして発展した。お台場に実物大のガンダムが造られる系譜は「ガンプラ」が確立されていたからこそありえたことではないだろうか。 ©創通・サンライズ
奥深いガンダムの世界
私はモビルスーツ(モビルアーマー)に「肉体」を、パイロットに「魂」をみる。ララァのエルメスが宇宙の「塵」になった時、ララァは「宇宙」になった。そこには「とりかえしのつかないこと」では終わらない、より高次なものへの想像をかき立てる強烈なメッセージがあった。当時、少年だった私はそれを「死」と受け止めなかったと記憶している。
「ガンダム」で「死の現象」がこのように多元的に描かれるシーンの原点であろう。「めぐりあい宇宙」という副題には「ガンダム」という叙事詩、神話の無限遠点が込められているように思える。
劇場用3部作第2弾の副題は「哀・戦士」。連邦もジオンもなく、理想をもとめるも理想にとどかず「哀」に散りゆくすべての者をさすのか。それはあたかも「人」と同義のようだ。
レビル将軍のいったニュータイプとは、戦争などしなくてもいい連中だよ
という言葉。シャアのいった今という時では、人はニュータイプを殺しあいの道具にしか使えん
という言葉。そしてララァの最後、解き放たれた意識が示した、人の本源性。
ジオン・ズム・ダイクンのみた可能性。人類種の次代へのファクターはテクノロジーではなく、宇宙の生命史において必然的で自然な変容にあるとするならば――私たちが生きる現在の現実世界は「オールドタイプ」そのものであり、誤解の重力に縛られつづけている。New(新しい)Type(基準)の暁光すらない。
誤解の重力から離脱できぬまま「オールドタイプ」による歴史の造設は今もつづいている。人間が誤解の限界を、臨界をむかえるまでに、誤解の極限状態としての困難を、葛藤を、いくつ経験しなければならないのだろう。すべての物事にはじまりと終わりがあるのなら、人が愚かさの終わりをみるまで、真に希望をみはじめることはないのではないか。
こういうと、因果を含めたララァの囁きが聞こえてきそうだ。
100億の時をかぞえる宇宙で、私たちが、いくつめの世界を生きていると思って?
むだなものなんてない。
高みにいたるためにすべては不可欠な事々――。
──
『機動戦士ガンダム 光る命 Chronicle U.C. 編集版』創通・サンライズ
さまざまな時空に降り立つガンダムは、「希望」、「いのち」の象徴なのか。現実と理想、創造と破壊。両極の狭間のスパークに浮かび上がる人の希望、いのちの現象のあるところ、ガンダムは転生する。
テクノロジズムの現代に、人の希望、いのちの象徴がテクノロジカリーに表されたもの、それが「ガンダム」なのではないか。そうであればこそ、ガンダムは「人型」である必要があった。主人公機が「アッザム」であってはならないのだ。
戦争における戦闘という現象を実際的に考えれば、兵器が「人型」であるのはリアリティーに欠くことだ。戦闘はおろか、土木作業、ピッキング作業においてすら、「人型」であるメリットはない。「人型」は人の感情が馴染む型ということがメリットのほぼすべてである。だからこそ、神話、文芸としてのガンダムはあえて「人型」なのだろう。
『機動戦士ガンダム めぐりあい宇宙』のポスターは、頭部を失ったガンダムが真上に一閃、ビームライフルを放つ姿だった。劇中、最後の敵、ジオングに頭部を破壊され、右脚を灼かれ、崩れ落ちるガンダム。子供だった私は、そこに「機械の破損」ではなく「ガンダムの最後(死に際)」をみた。それは「肉体」そのものだったのである。

『機動戦士ガンダム MS IGLOO』では人物もCGで描かれた。しかし、一昔前のゲームのムービーのようなマネキン感に違和感がつのったものだ。作画は手描きであれば歪みもでるが、パワーがある(ドアンザクの奇跡)。私はやはり機微あふれる手描きの作画が好きだ。 ©創通・サンライズ