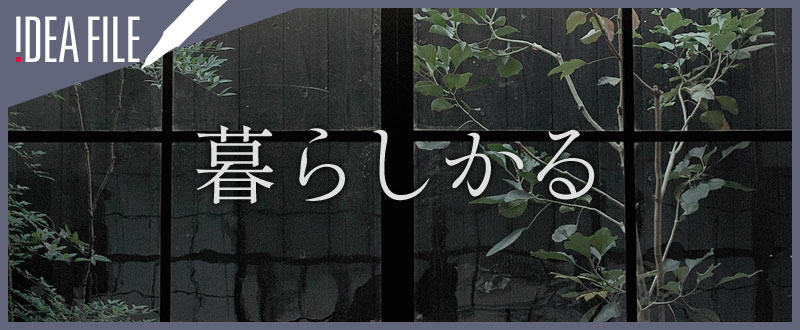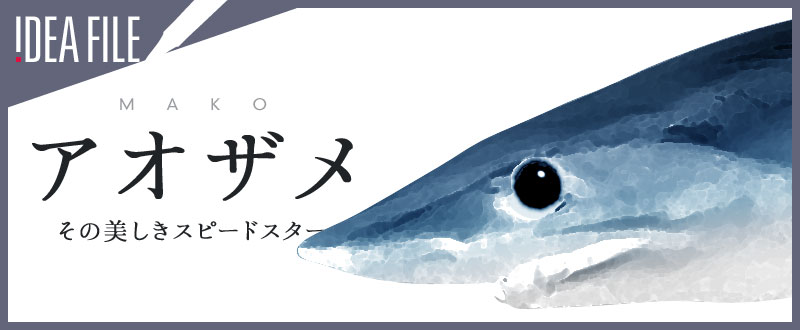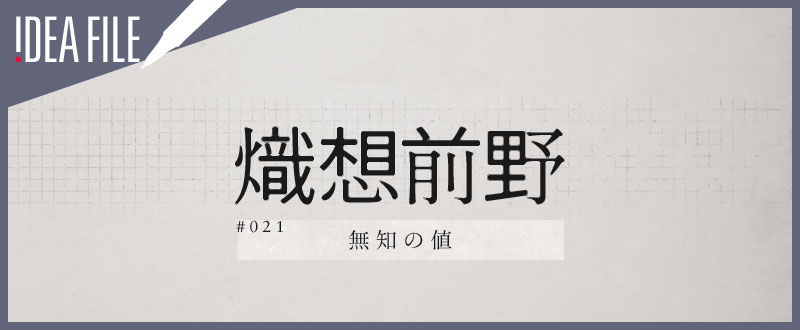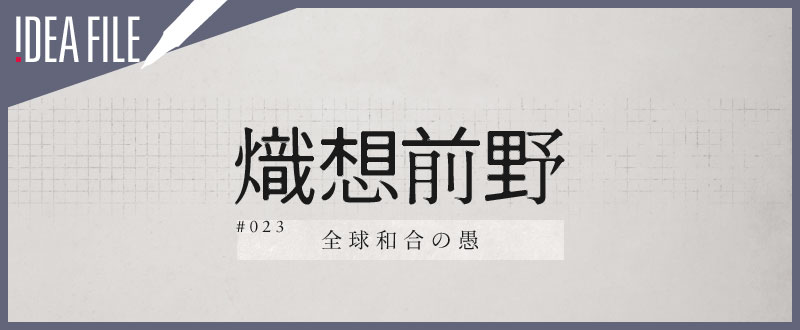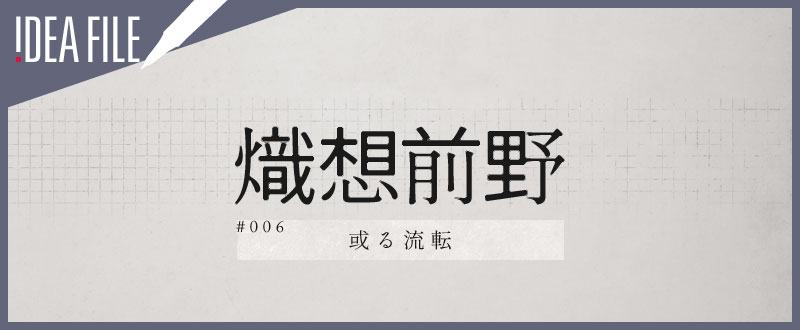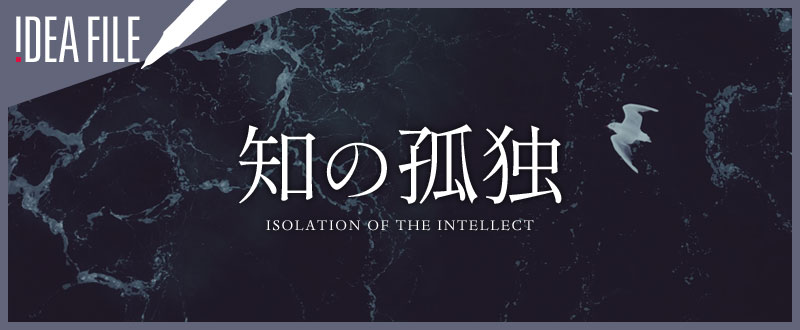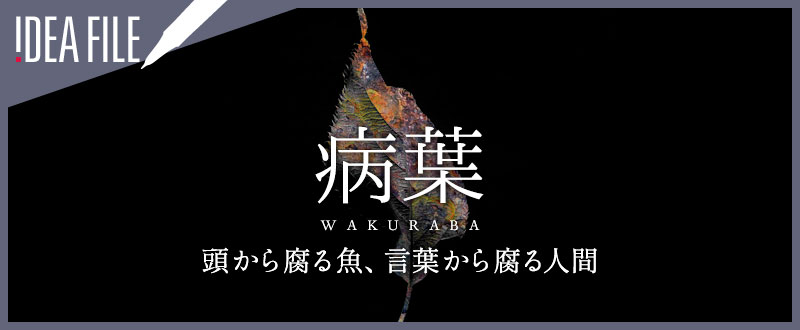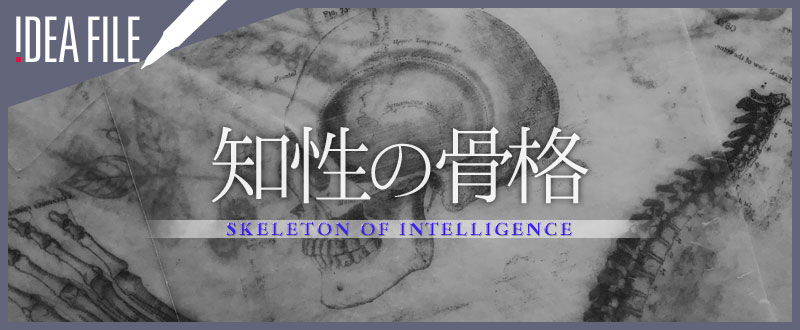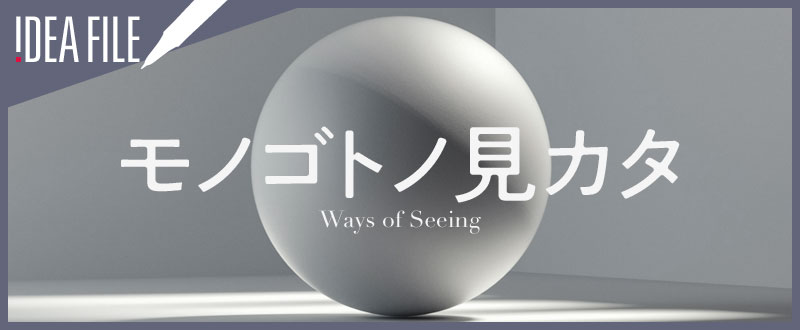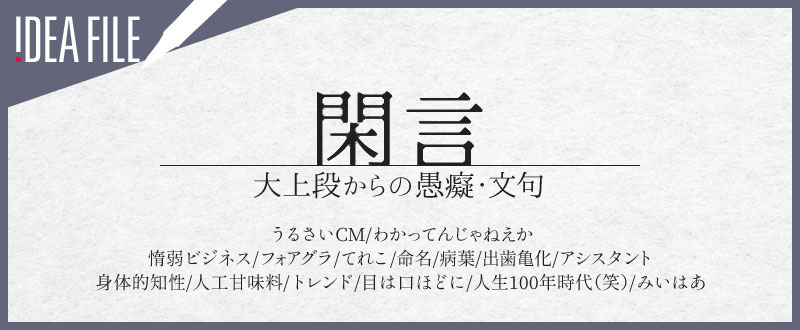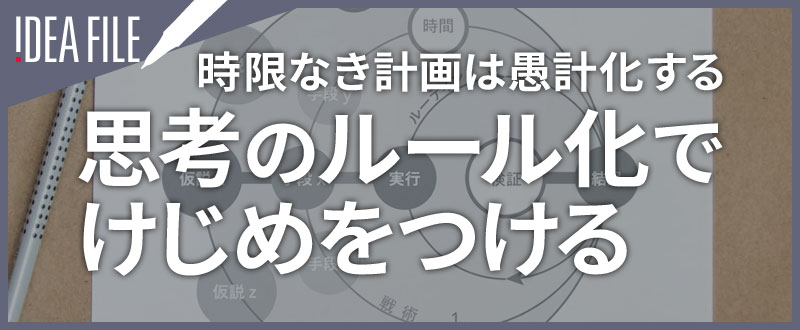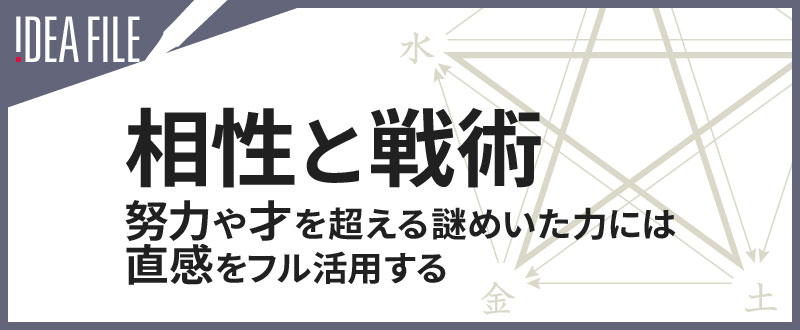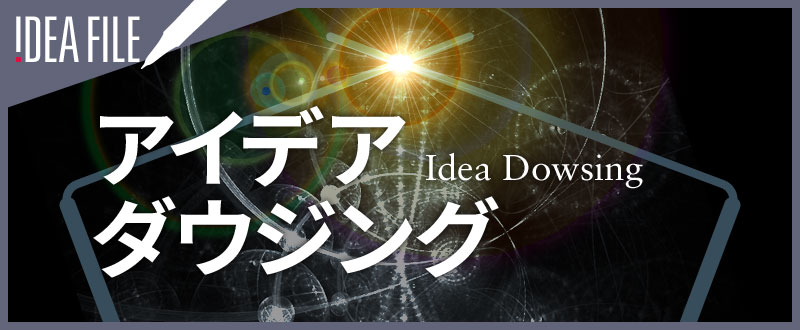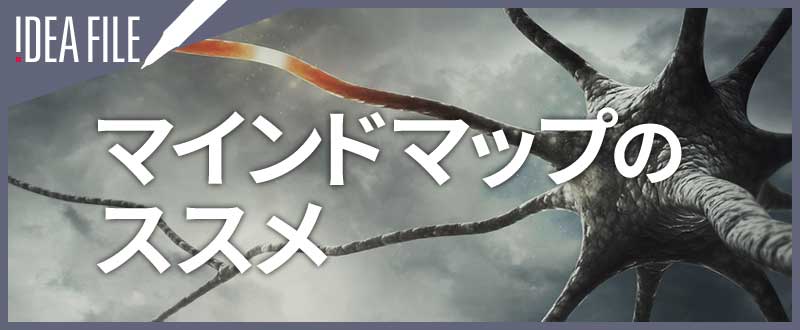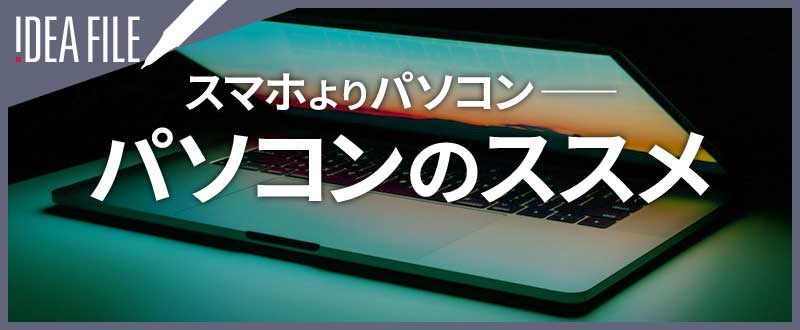スピリチュアルの不都合な話
スピリチュアル――端的に言えば、この世ならざるものによる(読解力の衰えた)現代人に向けたインスタントな悩み解決論か。
スピリチュアルというカテゴリー
書店で「スピリチュアル」とカテゴライズされた書架を見る度、「真実」としていない書店側は中立的であり冷静でよい、と思う。現代の超俗、脱俗を期待するもののための読み物と勝手に解釈し、手にとってみる。
なるほど、要は儘ならぬ世界での生き方について、歴史的知識のいいとこ取り、まとめ、Tips★1のようなものか。
物質を全的に観念とする考えはバークリー★2にみるソリプシズム(唯我論、独我論)、自己肯定の段取りはアドラー★3、といった具合か。ある意味、忙しい現代人に向けてよくできている。仏教や量子力学の知識も取り込み、その無範疇ぶりをまとめるのに地球外生命や高次の霊的存在が登場するのも適任だ。これではクレームのつけようがない。たしかに、これはこれでカテゴリーとして立つ。
端的に言えば、この世ならざるものによる(読解力の衰えた)現代人に向けたインスタントな悩み解決論か。
★1 Tips――もとは「助言」などを意味する英語。広義には便利なテクニックやコツを指す。
★2 バークリー――ジョージ・バークリー(George Berkeley 1685-1753)。アイルランドの哲学者、聖職者。
★3 アドラー――アルフレッド・アドラー(Alfred Adler 1870-1937)。オーストリアの精神科医、心理学者、社会理論家。
スピリチュアルの文体
スピリチュアルの文体の特徴のひとつは、すでに知られている哲学や科学の同種の論において、思想的課題として含まれる葛藤や可謬性には触れようとはしない。また、最先端だが既知の情報を脚色し、最先端のさらに先をいっているかのように言いまわす。
現在、スピリチュアル界隈でかまびすしい「量子」や「波動」という言葉も、これがプランクやシュレディンガー、あるいはハッブル宇宙望遠鏡の存在を俟たずにさけばれていれば、スピリチュアルもスピリチュアル学へと格上げされたかもしれない。しかし、その弁はいつも二番煎じ、哲学や科学の知識のファインチューニング、あるいは魔改造★4なのだ。
「引き寄せ」という象徴的な言葉にみるように、心さえあれば機能させうる――その論理のためには豪快な論法の使い分けもまた必要なのだ。スピリチュアルの新奇さはここにある。このような論理展開をするために、頻出するワードには偏りがみられる。次元、波動、目覚め、etc.
たとえばスピリチュアルにおける「次元」という言葉は、数学的空間のことではなく、事物を捉える視座のことでもなく、およそ「等級」の意味で扱われる。他者や社会と無縁では本来、機能しない等級、位階の概念だが、その標識への憧れはあるのだろう。本人の自覚、認識次第で自己完結できる次元は、自らに標識を与え、満たし、また知的シェルターとして機能するようだ。
波動にかんしてはどうか。事物はすべて波動である、との解釈に無理はない。しかし、では反射や干渉、回折といった波の性質について、スピリチュアルのその機序のより詳細な説明はあるのか。宇宙という大複雑系、大震動のなかで、波はむろん人間には予測不能な特性を揮うであろうなかで、インスタントに、随意に、まったく個人的に統御・運用できる波……。他の並の議論でも問われて然るべき疑義の欠片もなく、論があまりにも無抵抗に、半狂信的に進むあたり、傍らには胡散臭さと映じてもしようがないだろう。
「気の持ちようだよ」――それだけではさすがに自らを説得しきれない、ネット時代、情報超過時代の子らは、真理にすら時代なりの論理、修辞の尾鰭をもとめた。その結果、いつの時代にもあった救済法が、時代らしさを帯びて今、スピリチュアルとなっているのではないか。
素朴な年寄が心得ているような論理を、文体を変えるだけで啓示的にみせることは難しいことではない。じつはごく卑近、あるいは衆知の論理を高次的に修辞している、そのような文言が目立つ。年寄に言われると癪に障ることも、なにやら発光する宇宙生命からの言葉であればスピリチュアルになる、ということか。
プライドが高く、忙しく、いつもスマホにかじりついて耳年増、しかしカネには苦労しっぱなしの現代人をマーケティングしたかのようなスピリチュアルというジャンル。そんなスピリチュアルを私は一定、理解する。
技術によって情報は地球規模で開かれはしたものの、情報には人間個々の核心に根深く在る葛藤に平衡をもたらすほどの力はなかった――無意識的にかそれを覚った人々が、地上の位相そのものからの超脱を願い、地球外に、異次元に期待を寄せるのだろう。
書店に一郭をあたえられるまでに成長したのは、時代の心理とも合っているのである。
★4 魔改造――サブカル用語のひとつ。本来の意味や用途を大きく逸脱した形に改造することを意味する俗語(スラング)。
スピリチュアルをあえて語らず
私はといえば、地球外に知的生命はごまんと存在すると考えている。そのもっとも卑近な根拠のひとつは、数千億の天体の存在が確認されているにもかかわらず、地球にしか知的生命が存在しないという証明の方が、一般的にいってはるかにむずかしいことだ。宇宙はおそらく生命だらけだろう、日本一混んでいるといわれる東京メトロ東西線よりも。
さりとて「私の愛読書」としてスピリチュアル本を挙げるのには抵抗があるし、私にとって実際にそのような書物にはならない。
物質を全的に観念とする前提にもさしたる意味はない。この世は夢でなんらかまわない。問題は数十年にわたって継続する、絶えず危機をはらんでいるこの夢への対処である。
コギト・エルゴ・スム(思う、故に、在る)
という分割不可能な主体の次元において、主体が神経から成ろうが神性から成ろうが、そんな前提は実践においてどうでもよいことである。
哲学の問題など、人が人生に本気でゆきづまるや、瞬時に蒸発してしまう
とシェストフ★5はいったらしいが、それが実際だ。衣食足りてスピリチュアルにはしる――論理を組み立てる力仕事や読解力のなさを地球外生命や霊にアウトソーシングしているあいだは、主体であるスピリット(精神、霊魂、spirit)は正念場に立ってはいない。
過去、数千年あるいは数万年起こらなかった飛躍的な現象が、近年、人類に起こるのだという――私はいわゆるUFOといわれるような刺激的な飛行体を何度か見てはいる。しかし、それが地球外生命のものでも、エリア51の機密の産物でも、何がどうあれ一足飛びにはいかないのが人生というものだ。人生に飛躍を期待するのは、飛躍が一時の抗鬱剤であることを知りつつ服用する、すでに鬱にとらわれているものの傾向である。
創造主のような全能感を感じられなくてもいい。大小便を繰り返すネズミやサルと変わらない一動物でまったく問題ない。だからそろそろ人間同士、本気で、地に足の着いた「スピリチュアル(精神的な、知的な、spiritual)」な話をしないか?
★5 シェストフ――レフ・シェストフ(Lev Isaakovich Shestov 1866-1938)。ロシアの哲学者、文芸評論家。