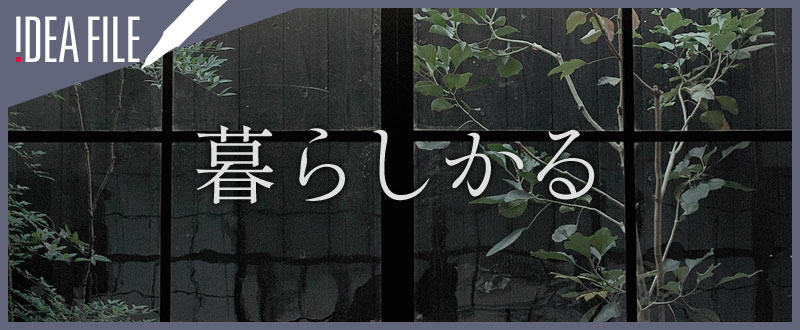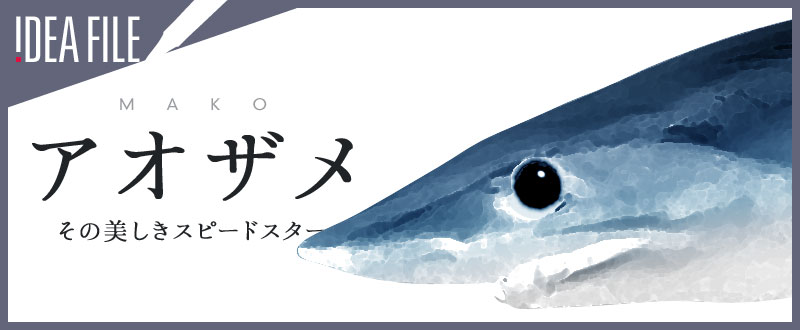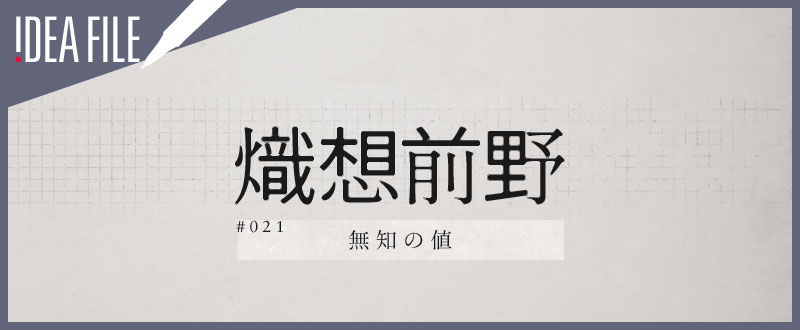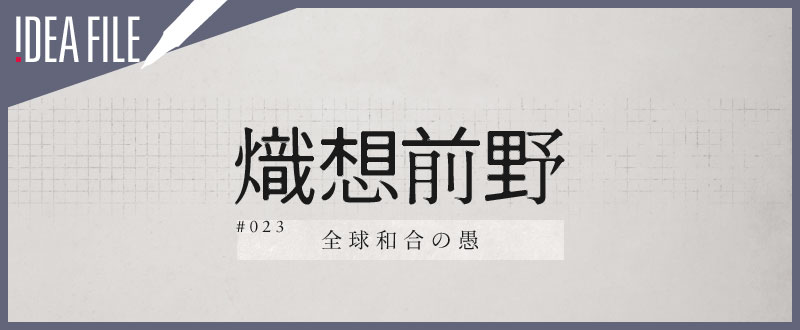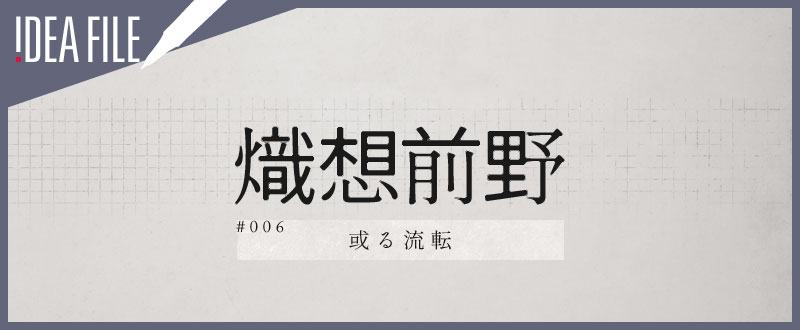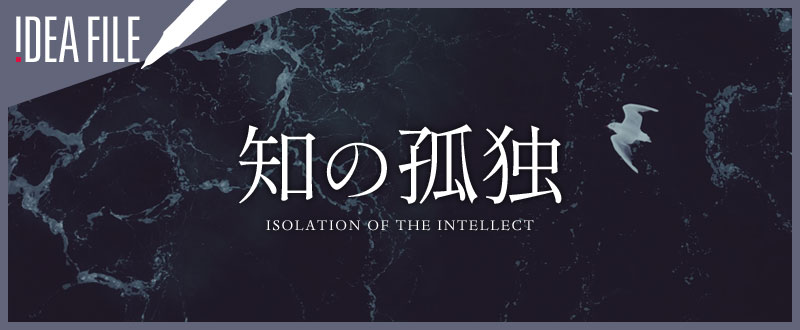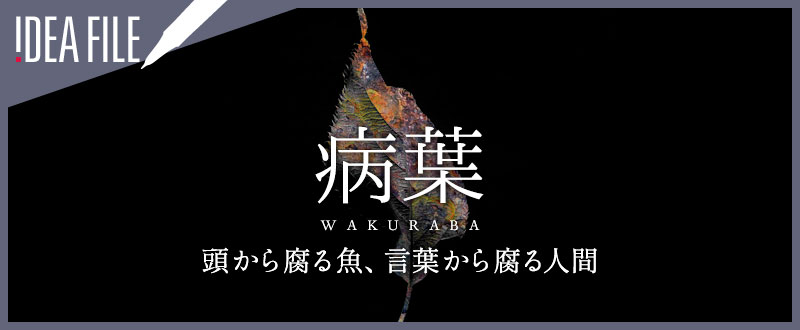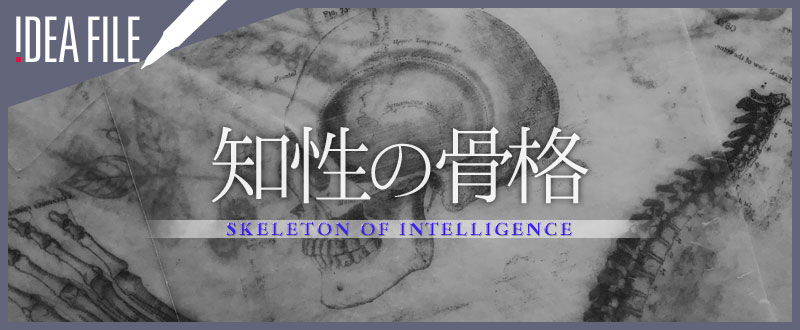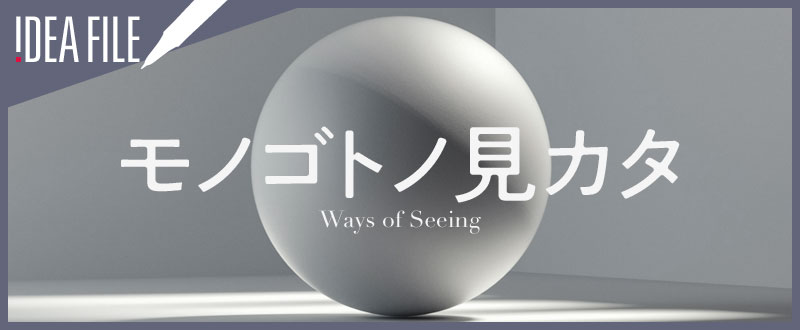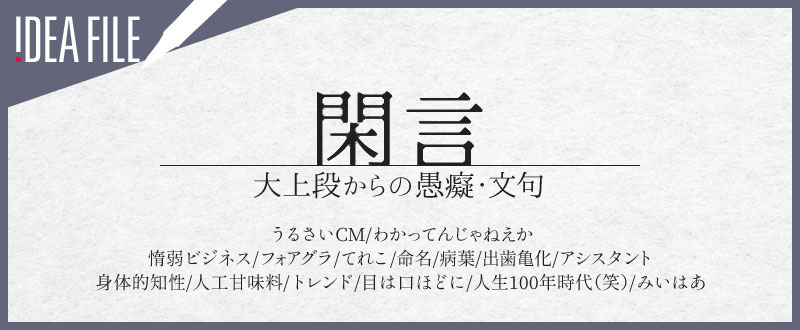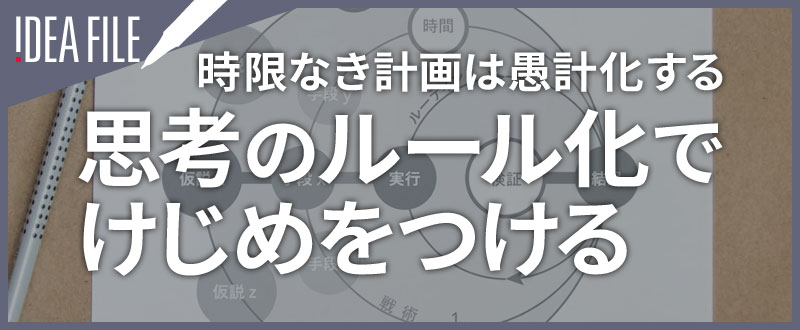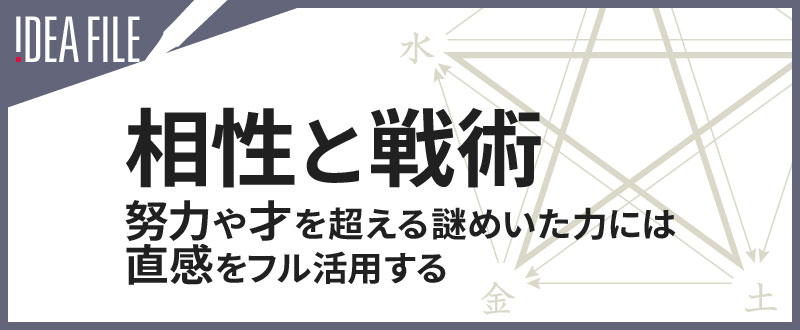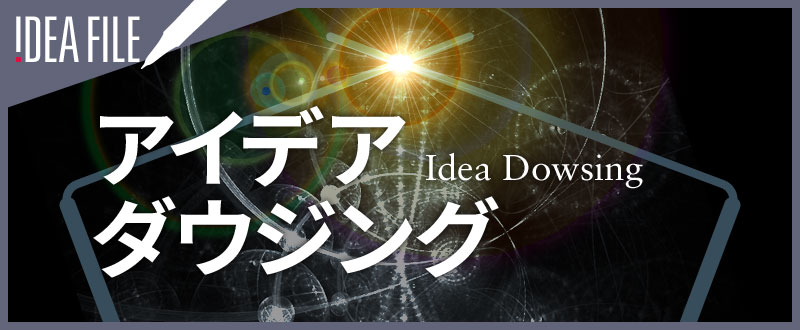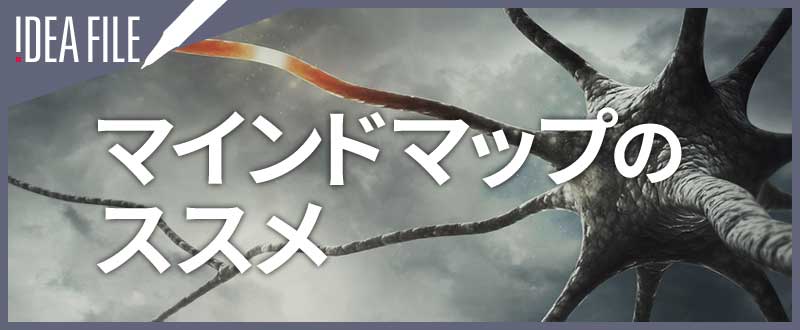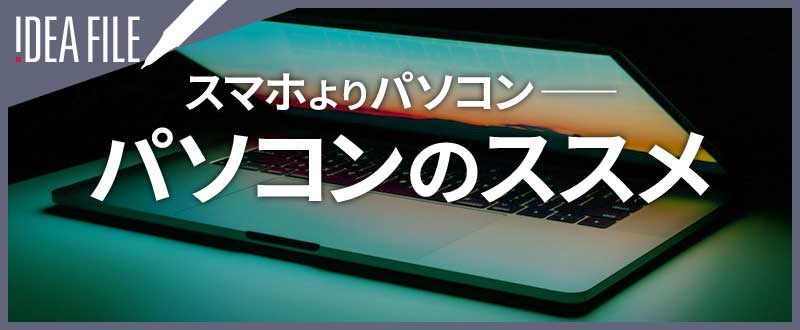脱結論
「結論はあれか、これか」――誰も彼も黒白をつけたがる。つけたくてしようがないらしい。しかし拙速にだしたその結論もしばらくするとボロがでて、またどっちつかずで右往左往することになる。毎度のように結論に裏切られるのは、およそ結論というものが短期的、局所的には成立しないものだからかもしれない。巨細つつみ込むような視座をもつ老子のアイデアを拝借し、「脱(矮小な)結論」を展開してみよう。
その天国のイメージはいかがなものか
「極端だなあ」と思う。
「結論は、こうだ」――誰も彼も黒白をつけたがる。つけたくてしようがないらしい。それは相当なマニアックな状態だということに、どうやら気付いていないとみえる。
たとえば「脳なのか、意識なのか」という問いについてはどうか。脳から独立してあるとされる「意識、魂、霊」といったイメージ。そこから語られる霊的次元、霊的世界観のなかでも「天国」というイメージに物申す。なぜなら一般に語られる霊的世界の象徴たる「天国」のイメージは、単に「脳」が考えるところの「至福」ではないか。完全なストレスフリーの状態、願望を指して「天国」とよんでいる。
霊的世界のイメージはすべてこの世の知識で埋め尽くされている。これに対して「アプリオリ★1として霊的世界があり、その反映としてこの世があるのだ」という論は少々、乱暴だ。それは結局「機械仕掛けの神(deus ex machina)★2」をもちだすのと同じである。巧遅は拙速に如かず
とはいうものの、生命の旅路の「結論」にしては拙速が過ぎるのではないか。

人間(肉体)、空間(自然)、天使の羽根(鳥類)等、すべてこの世の知識が素材となっている。人の知識が変われば霊的世界観もSFも変わる。フィクションのイメージすら知識の反映でできている。
★1 アプリオリ(a priori)――「より先なるものから」の意。経験にもとづかない先立つ認識・概念。経験的根拠を必要としない性質。
★2 機械仕掛けの神(deus ex machina)――矛盾や破綻が生じたときに都合よく登場させられる神。
「ある」と「ない」が「有る」
「脳なのか、意識なのか」――喧々諤々やっているさまに、老子のアイデアを思い出す。
三十輻共一轂。
当其無、有車之用。
(中略)
故有之以為利、無之以為用。
――
老子「無用之用」
意味はこうだ。
「30本の輻(スポーク)は1つのこしきに集まって車輪を形成する。
そこにある何もない空間が車輪としての機能を果たす」
この解釈はきわめて総合的だ。
現象を局在的に対象化した視座から突き詰めるのは人間の悪いクセのようだ。「脳なのか、意識なのか」という問いを「無用之用」の視座で俯瞰してみよう。そうすると「なぜどちらかに答えを求めるのか。どちらかでなければ都合の悪いことでもあるのか」問いが返ってきそうだ。
つまり、心的なものと脳との関係は、一定不変の関係でもなければ、単純な関係でもないのである。演じられる戯曲がどういった性質のものであるかに応じて、役者たちの動きが当の戯曲の内容について教えることは、多くなったり、わずかになったりするだろう。パントマイムであれば、ほとんどすべてが言われるだろうし、洗練された劇なら、ほとんど何も分かるまい。それと同じように、われわれの脳の状態が心的状態をどれほど含むかは、われわれが自分の心的生を行為に外化しようとするか、それとも純粋意識に内化しようとするかに応じて変化する。
――
アンリ・ベルクソン/杉山直樹訳、『物質と記憶』講談社学術文庫、2019年
これを先の老子の言葉と合わせてみよう。車輪を観察していて分かるものと、車輪と緊密なつながりはあるが、車輪を観察していても分からないものがある。前者はたとえば路面の状態や速度など。後者はたとえば目的地である。しかし後者の分からないものについていえば、車輪という物体のみを所与の対象としているから分からないものになるのだ。
総合的にみれば、そも「車輪」なるものが存在するのは移動のためだろうという推理は自然だ。移動するのはなにか目的(それが運動そのものでもかまわない)があるのだろうという見通しも立つ。
見るべきものを見るのではない、見えるものしか見ないことが科学のみならずすべての思惟の悲劇である。よく知られているように、人間が視覚で捉えられるのは電磁的にみても宇宙のほんのわずかな部分、矮小な世界にすぎないのだ。その意味において、ジョン・レノンがいったImagine(=想像して)
はじつに冷静にして正鵠を得ている。
脳という輻とそれ以外のなにか(不可視)が総和としての「意識」という機能を生じさせるという可能性。総和してはじめて確認されるもの――たとえば「1+1」だけでは「2」という数字は表れていないように。常に全体性という関係性、総和が宇宙という表れであることを鑑みれば自然な可能性だろう。
「ある」と「ない」が「有る」。往々にしてそういうものだ。太陽系に喩えれば、太陽と八つ(?)の惑星といった実体は輻。系全体はヘリオスフィア(Heliosphere)とよばれる太陽の影響圏、つまり不可視の場だ。どちらといわずその総体を「太陽系」とよび、そうしてはじめて機能している。
老子のいうとおり、有の価値を無が、無の価値を有が、"一円(総体)"としてあらわすのである。
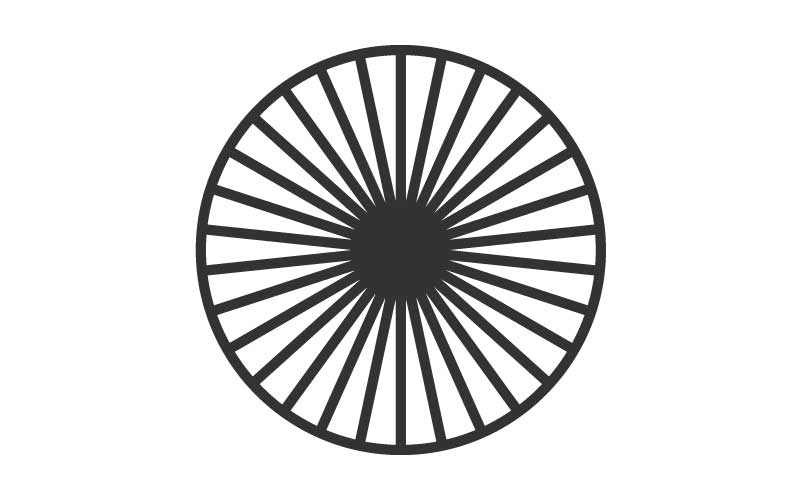
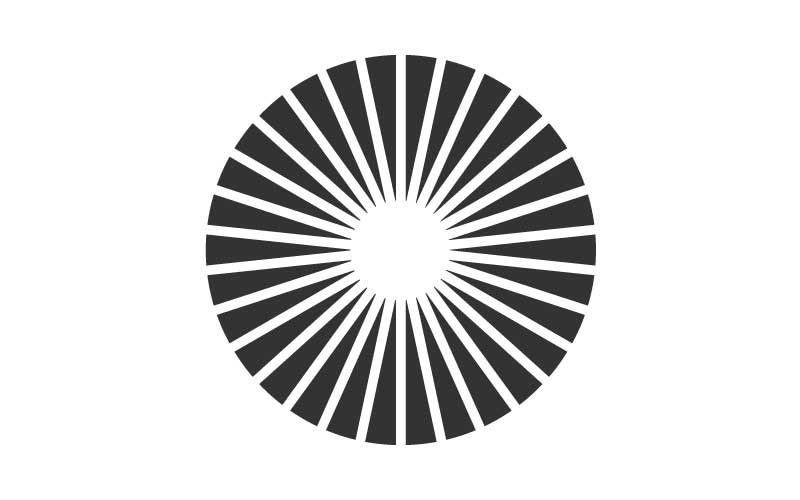
輻という有はその内になにもない空間を生み、それが機能を生む。
意識・心の危うい定義
我々が独立してあると考えがちな意識、心とよぶもの。これが視点によってはいかに危うい認識であるか、例を挙げれば枚挙にいとまがないが、なかでも分かりやすい例で話をしよう。
「ハリガネムシ」という寄生虫がいる。カマキリの尻から出てくるあれだ。子供の頃はこいつでよく遊んだものだ。
このハリガネムシは寄生したカマキリを操作する。いわゆる「マインドコントロール」だ。ハリガネムシは水中で産卵するため、宿主である陸生昆虫のカマキリを水に誘い込む必要がある。そこで内部からカマキリを操作し、水に飛び込ませるのだ。傍目にはカマキリが自らの意思で水に飛び込んでいるようにしかみえない。もしかすると、カマキリ自身もそれを「自分の意思」だと信じているかもしれない。
人間もいわば腸内細菌やミトコンドリア、遺伝子といったものの容器、宿主である。それらミクロなファクターXの相関の結果を自分の意識、心とよんでいる可能性。その可能性を完全に否定できるものだろうか。
あるいはマクロな視点で、地球上の全生命が例外なく影響を受けている太陽系の、銀河の、宇宙のシステムの見えざる要請。それをあたかも自分の意識、心とよんでいる可能性。
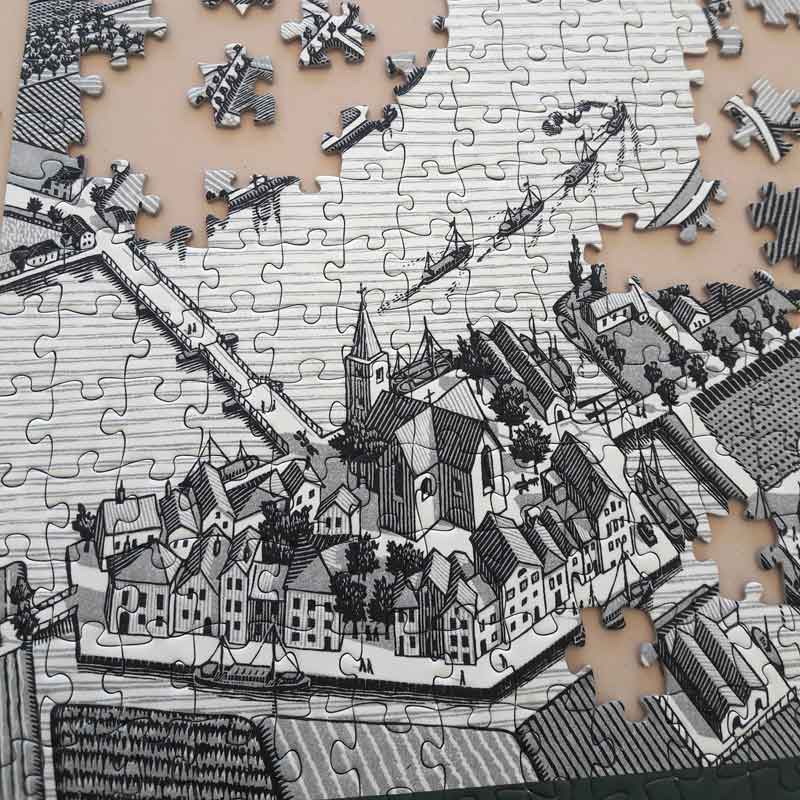
ジグソーパズルの1ピースから全体を想像することは困難だ。しかし全体から抜け落ちた1ピースの箇所を見ると、それが全体のうちの何を担っているのか想像することは容易だ。
専門性一辺倒の学問はバカの一つ覚えと紙一重
宇宙の現象は「専門家」によるものではない。これは専門知というものがどこまでいっても過程への、時間的・空間的局所へのはたらきかけにすぎないという自明だろう。その意味において脳と意識が一体全体どうなっているのかという問いとその解は、次のような問いとその解とそれこそ並行である。
「人間と人間らしさとは一体全体どうなっているのか」、「音楽と感動というものは一体全体どうなっているのか」――。
「機械仕掛けの神」をもちださなくとも世界は説明できると信じるのはけっこうなことだ。しかし細部に宿り給うた神が同時に遍く全体に宿り給うという業から、むしろ遠ざかり続ける人間の専門性への没入。そのことが結局、苦し紛れの「機械仕掛けの神」をいつまで経っても持ちださざるをえなくするのである。
天国だと信じるものが、目指すものが、はたして本当に天国なのか――ファクターXの相関の結果や、見えざる要請によるもの、あるいは錯視――可謬性というものを天国の門前に掲げねばならない。
結論は専門家に――この誤謬によってどたばた悲喜劇が次々と露呈したのがコロナ禍だったのではないか。物的に捉えられるウイルスと、場としての非物的な社会という全体性。ウイルスという極小の構造体は突き詰めて、しかしそれにまつわる対策によって社会という不可視の全体にどういう結果が生じるのかを突き詰めて予測、考えただろうか。危なっかしい結論なら、だすのはやめちまえ、どうせ結論にはならないのだから、とすら思う。
そして今日も、世間というものはまったく「極端だなあ」と思う。