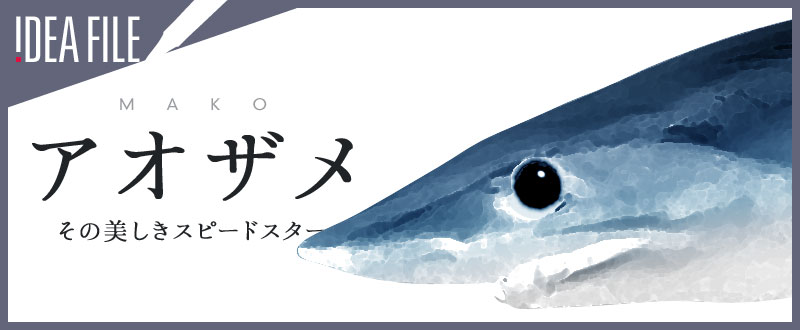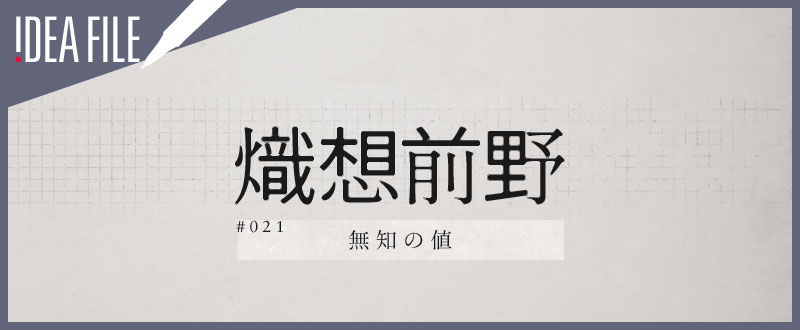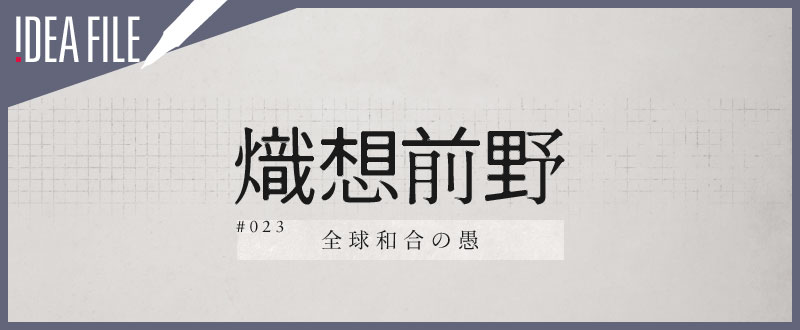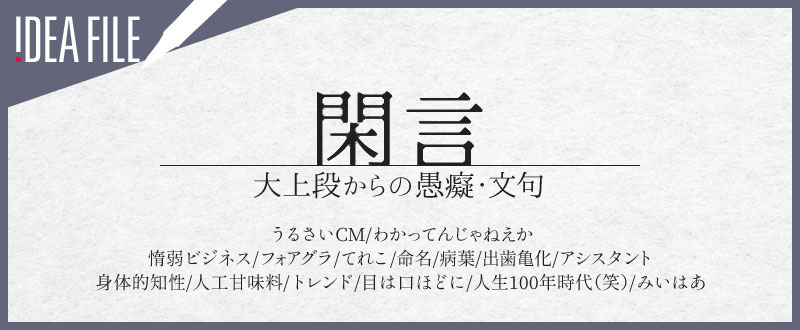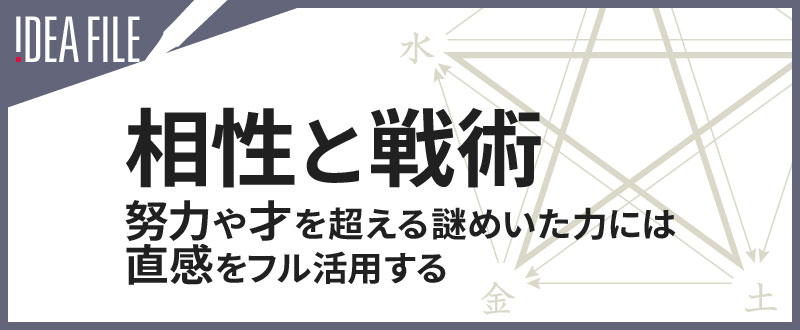文化的知性と鬱
「無限の可能性」という言葉に無条件に期待を抱くのは、単に少年誌の漫画に淫した影響である。「文化」という言葉に懐古や形骸の観念を紐付けるのは、単に語義の貧弱である。「文化的なるもの」を破壊して「無限の可能性」へ突き進む世人の大行列は、単に「鬱」によって魯鈍になった知覚の反応である。現在、世人の多くは医療機関の判断を必要とするまでもなく「鬱」を患っている。「文化的知性と鬱」の関係を論じる。
技術が導く無限の可能性、
その先に待つ不都合な真実
無限の可能性――惹句によくみられる、「未来」に掛けて使われることが多い言葉だ。つまり「何も決まっていないこと」を良き価値として修辞する常套句であり、「自由」とほぼ同義である。一頃、ちんけなブラック企業のキャッチコピーにも「アットホーム」とならび大量に使われたものだ。――無限の可能性がキミを待っている!
「可能性」や「自由」は換言すれば膨大な非決定分である。そして、行為とはその中からかならず一つを選ぶことだ。無数の未知の暗い穴の一つに手を突っ込むようなこと――それが「可能性」や「自由」にたいする行為の内実だ。
そのような選択についてまわる恐れ、リスクからより解放されよう、技術のチカラによって――そう意気込むテクノカルトたちが現今の嚮導者となっている。
高度情報化社会を「可能性と自由の増進」などと信じて疑わない徒輩は、思考と現実を対照させる労を端折りすぎではないか。無数の未知の暗い穴を技術的計算によって知悉し、流布せんとするその行為。それがすでに「可能性」や「自由」への「挑戦」ではなくニヒリスティックな「放棄」へのプロセスだからだ。
その計算結果を与件とする高度情報とやらのみを合理とすることによって、選択はきわめて平板化する。とりもなおさず「可能性」や「自由」それ自体に機械的縮減という結果しかのこさないのである。
耳目を集めるAI(人工知能)も、じつのところ非決定分の増殖に耐えかねたNI(自然知能)の介護知能的な性格が色濃い。行為のための選択作業をNIがAIにアウトソーシングしはじめたようにもみえる。もはや「可能性」や「自由」を取り扱う術も気力も失った知性は最後、自己意識にすら価値を見出だせなくなる。「明るい展望」すら自力で描けなくなったヒトは、「鬱の生命」へと堕するのである。
鬱乎、鬱蒼、鬱閉、鬱々――「鬱」とは「草木の生い茂るさま」を意味する。
「大量」で「高速」だが「質」はいたって平板きわまりない情報ならぬ冗報(「冗」は無駄、余計の意)に四六時中、耳目をかたむける。そりゃ「鬱」にもなる。ならないほうがおかしいというものだ。

「大量」で「高速」だが「質」はいたって平板きわまりない情報ならぬ「冗報」の鬱の森。針路も、その判断基準も失った状態もまた「鬱状態」である。
文化的(cultural)なるもの
「無限の可能性」などまっぴらごめんだ、というほうが冷静なのだ。そこから、手に負えぬ「無限の可能性」のデザインにかられ、帰納と演繹の遠心分離機にかけ、抽出した妥当。「時効(熟成)の証明」を得た妥当性。持続可能な価値の基準。それを「文化的(cultural)なるもの」とよぼう。
「文化」とはつまり平衡術である。人間にとっての「無限」における行為の最大限度幅、あるいは「可能性」や「自由」がかろうじて安定する規範といってもいい。
語義の乏しいものは「文化」といえばすぐに古めかしい建築物や工芸品の形式的特徴、因習・陋習の負価値なイメージにはしる。あるいはアンシャン・レジーム(古臭い制度や体制)と同一視する(ちなみに、文化の欺瞞、暗黒面は、それらよりはるか深遠にある。その次元では文化もまた精神の牢獄になりうるのだが……)。そんな皮相な解釈で済ませてしまうから「文化なぞさっさと捨てて改革を」となり破壊が猖獗をきわめることになる。
「文化的」とは、「無限」の取り扱いは超越の次元にまかせ、人間の解釈と表現でヒューマナイズすること、デザインすること。「鬱」という無規範に茂る雑木を「時効(熟成)の証明」という強金の斧で切り開いてできる、人に適当な道(価値)のことである。
つまり無限の可能性から文化にたどり着くのだ。「文化」を破壊して「無限の可能性」を突き進もうというのは「退行」である。 知のプロセスとして逆順なのだ。文化は実際的(practical)なものであり、文明は実験的(experimental)なものであるという事の素性を知れば、こんなことは自明である。
「秩序」は「パターン(型、様式)」として現象する。「文化」とは、言わば「死」としての「混沌」から「生」としての「秩序」へと向かう知力の自己組織化、エネルギーの本源的流れ、すなわち道の具象である。
「可能性」や「自由」とはその道における延伸、拡幅、支線、進化のことであり、道をそれて藪に踏み入ることではない。


有限の知性である人間は、際限なく求めることより、意味と価値の彫琢に注力すべきではないだろうか。
鬱の淵源
現今の技術とそこからの提案がなぜ人を鬱にするのか。要するにこういうことである。
今や技術は制度、慣習等の体系の制御破壊と新プロセスの間断なき反復運動の機関のことだ。それゆえ技術によって現実から耐久性が失われる。失われた耐久性に代わって短期的刷新が前提の新制度がもたらされる。だが、その価値は人とのつり合いがとれない。
なぜなら「組織」が敷く新制度・新情報なるものの意義は、組織という無生物(生活機能をもたないもの)的利潤である。生物(生活現象)としての「人間」と、本源において相容れない。今や「変革機関」の体をとる「組織」と「人間」との不親和の乖離は拡大する一方である。
天然界をみても明らかなように、生命は常に「維持機関」を礎とする。本来的に、生命にとっての「変革」とは漸進的にもたらされるべき現象だ。急進的である場合、それは「カタストロフ(破局)」といった破壊的現象となるのである。
生命とはその本質において間断なき「変革」をもとめるものではないし、対応できもしない。ライプニッツがいったnatura non facit saltum(自然は飛躍せず)
の言葉どおりである。
過去幾多の経験から、総合的平衡をとるための「知の精髄」を内蔵するものが「文化的知性」である。変革・改革・革新に対するものではなく、それらの仕方について指導原理として機能し、合理の前提となり、包摂もする上位の概念なのである。

変化による利益と損失について、損失の確実性と利益の可能性を秤にかければ、変化は漸進的であるほうがよい
というオークショットの見解もまた、文化的見解といえる。文化的思考は革新を否定するものではない。革新におけるリスクにたいし、軟着陸可能な速度は歴史をはじめとする時効(熟成)の証明からもとめよということである。
暴走する組織を見限り、
共同体へ目を移す
技術が自己増殖系となり、不可逆性と過剰性とをむき出しにし、人間の共同体をことごとく「組織」へと線維化しはじめた。こうなってはもはや技術に期待するところはないにひとしい。
この文明はやがて文化を蚕食し尽くすだろう。文化は公共から姿を消し、個人的観念のシェルターの中、古美術品のようにおかれることになるだろう。思惟の実体としての「文化的なるもの」は、かぎられた表現の場を個人、あるいは共同体へ移す。それはあたかも縷々としてつづく時の道、剛堅な知の大樹が一滴の水に映り込むようなものだ。
「鬱」に覆われ、みるみる生気を失って、どうにも気色がわるくなった「大世間」より「小文化」にこそ知性の生彩を観る。
これからの時代、個の生における「文化的なるもの」は、知と生の意味と価値における最後の砦となるだろう。

これまで歴史の時空に内蔵された「文化的なるもの」はこの先、マイノリティとなる「文化的知性」に内蔵されることとなる。