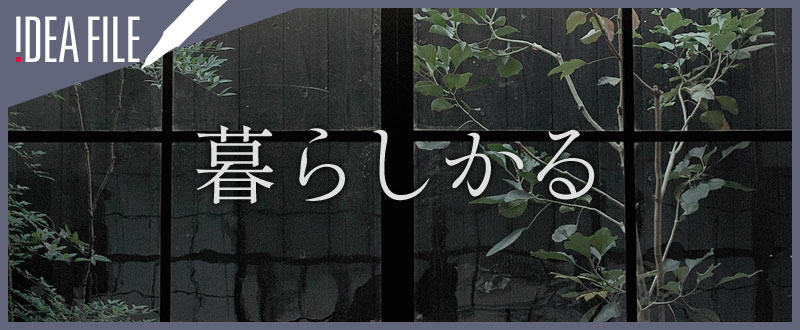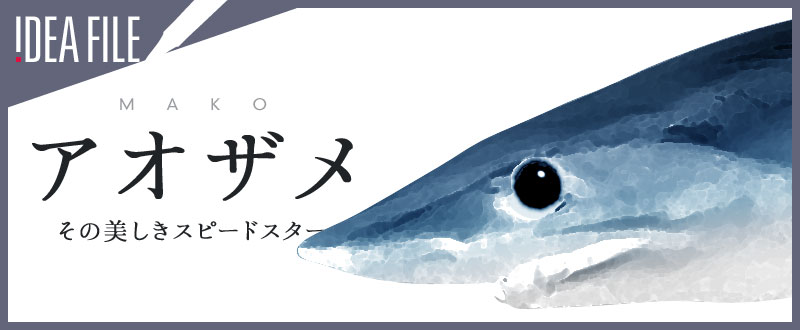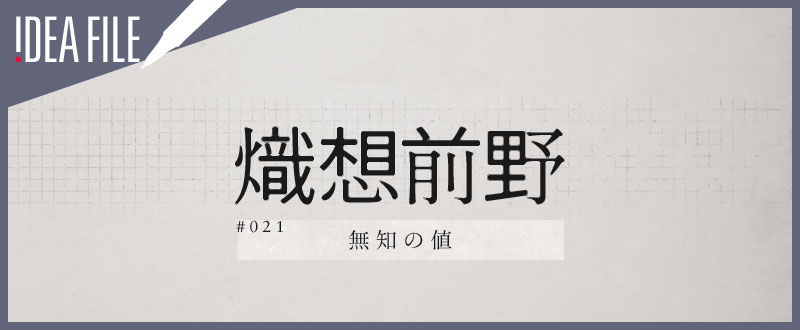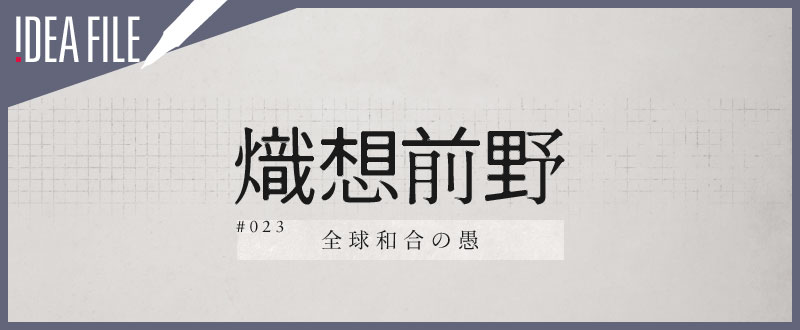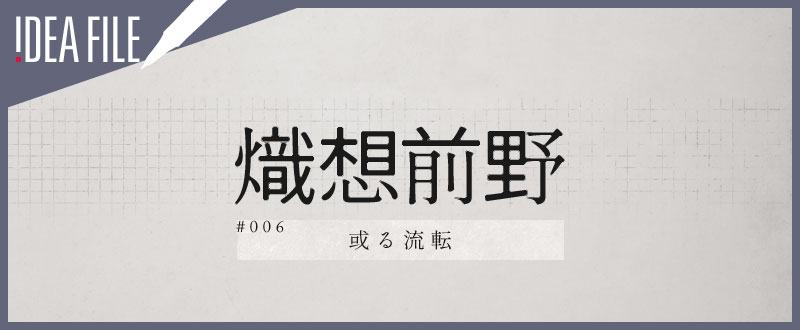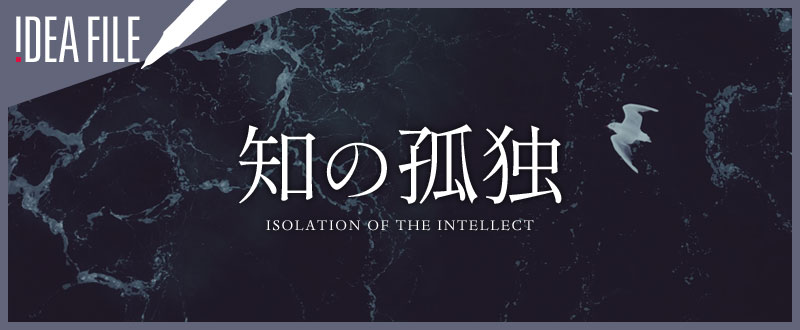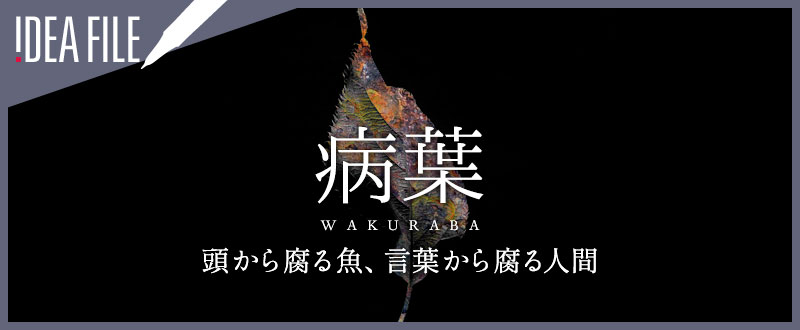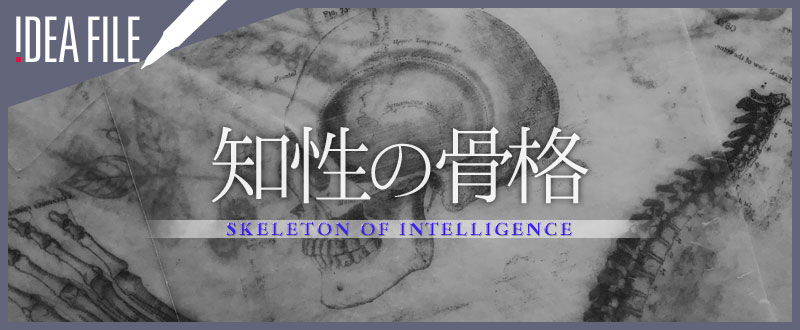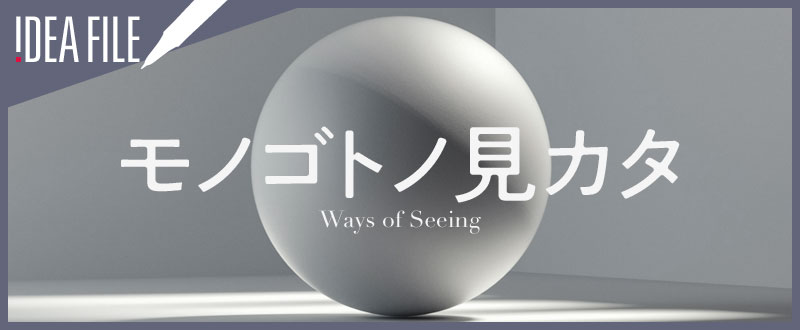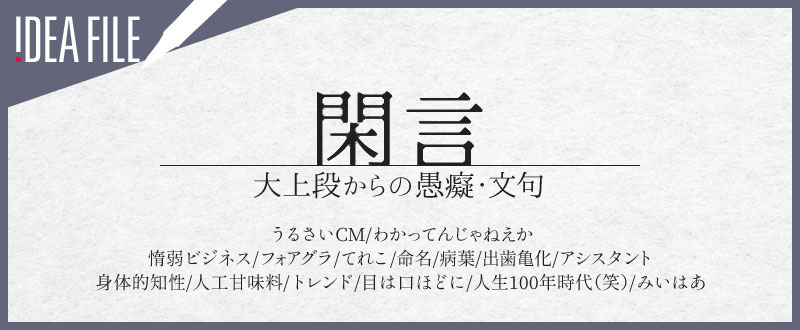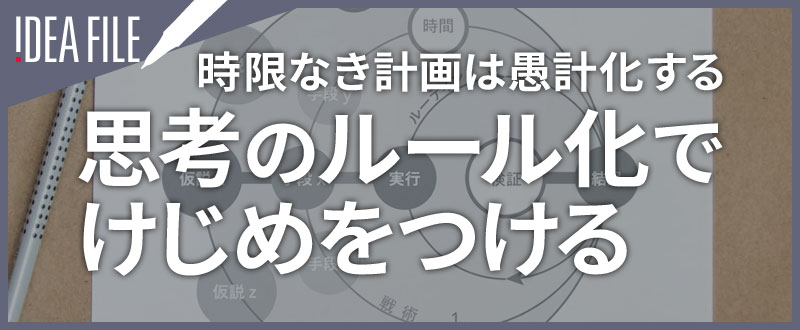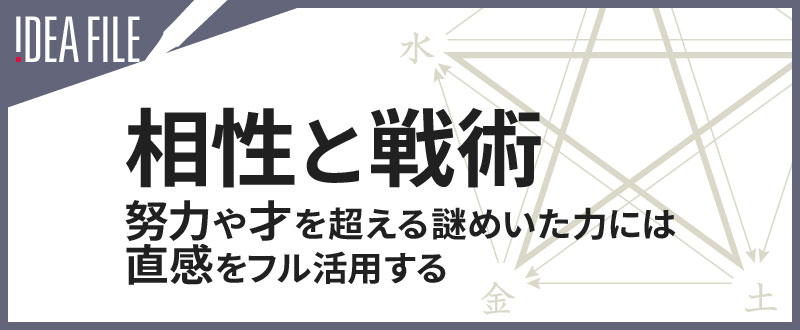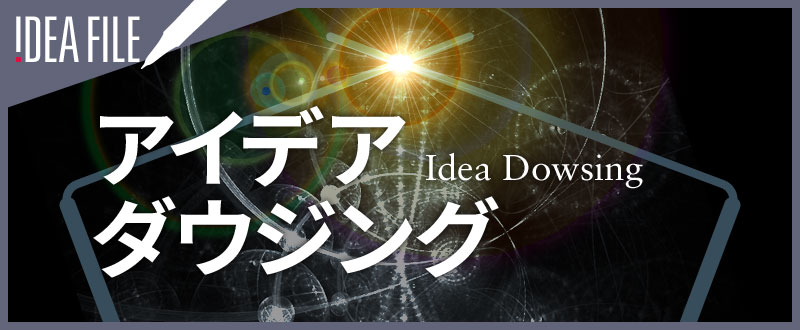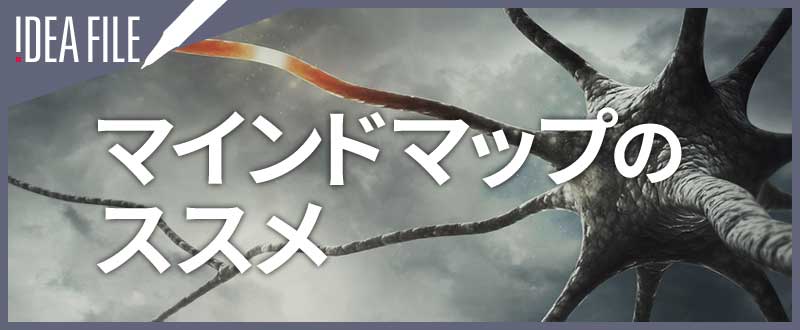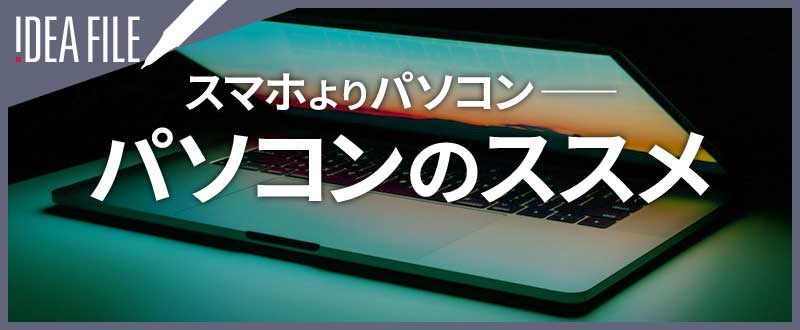及ばざるは過ぎたるに勝れり
アルントシュルツの(刺激)法則
「アルントシュルツの刺激法則」に及ばざるは過ぎたるに勝れり
を観てとり、今日只今の経験と事実の理解に利用してみてはどうだろう。じつはよくある「弱きは助け、強きは挫く」ということ。
アルントシュルツの刺激法則
「アルントシュルツの刺激法則★1」というものがある。神経や筋にあたえる刺激について述べた法則であることから、もっぱら整体やマッサージの専門用語のように使われている。どのような法則かといえば、
1弱い刺激は働きを活性化させる
2中程度の刺激は働きを促進する
3強い刺激は働きを抑制する
4非常に強い刺激は働きを停止させる
というものだ。「Arndt-Schultz curve」ともいわれる曲線で以下のように表記される
整体やマッサージの強度について頻用されるこの法則を、本論ではすこしばかり深い解釈で扱う、というより、実証された原理や法則というものは、真理の無限、その一郭に光を当てるものなのだ。整体やマッサージにのみこの法則を用いるのは浅薄である。
★1 アルントシュルツの刺激法則――ドイツの医師、ルドルフ・アルント(Rudolf Arndt)と、精神科医、ヒューゴ・シュルツ(Hugo Schulz)によって提唱された。
弱きは助け、強きは挫く
アルントシュルツの刺激法則は一般的な事物にも適用可能だ。
たとえば、人や動物とのコミュニケーションにおいて、最初はささやかな態度で警戒心を解き、小さくとも信頼を得(働きの活性化)、アクションを漸進的に中程度にし、より親密で強い信頼へと進める(働きの促進)。だが、ここで相手の複雑で繊細なテリトリーへと強引に押し入ろうものなら、警戒され信頼を損ない(働きの抑制)、さらに無神経に強度のコミュニケーションを強いれば、最悪の関係になり、破綻する(働きの停止)。今どきの若者に社員旅行を強制し、ブラック企業認定されるというのも強すぎるアプローチが招く「働きの抑制・停止」であり、筋組織も人の組織も似たようなものである。
投薬のような事柄においても同様だろう。最初から高用量の薬で治療に臨めば、瞬間的効果は得られるかもしれない。が、疾病の根治という包括的な計画、目標への過渡において、疾病の原因が高用量の薬剤に耐性をもってしまうかもしれず、そうなるともうその薬は使えなくなる(働きの停止)。あるいはアナフィラキシーショックのようなネガティブな反応を起こしてしまうかもしれない(定常状態 steady state の破綻)。「いっそ何もしなかった方がまし」という結果を避けるには、もとい刺激には、それなりの知識と技術が必要なのだ。
こういったことは「中庸」、「中道」、あるいは「保守」といった概念でより包括的に明示されてきたことだ。
そも、実証された原理や法則の窮極の意味と価値は「真理への漸近」にある。混沌かつ複雑をきわめる経験的事実の、人間が取り扱い可能なレベルへの秩序化。記号化でもあり、真理の了解方法となってはじめて、原理や法則は真骨頂を発揮する。
「アルントシュルツの刺激法則」に及ばざるは過ぎたるに勝れり
を観てとり、今日只今の経験と事実の理解に利用してみてはどうだろう。
宇宙は、人には到底、制御不可能な力で満ちているにもかかわらず、我々はそのかけはなれた力をまったくといって意識することなく、せいぜい天気などを気にする程度で生きていられる。それは宇宙というものが生命という現象にたいし、強い刺激を揮うことなく、もっとも程好い力でもって接しているからだ。宇宙的にみて、それは弱い力であろう。
弱きは助け、強きは挫く。
及ばざると見える力にこそ、事物の要諦が宿っているものである。

強すぎる力はバランスをもたらさない。破綻させるだけだ。