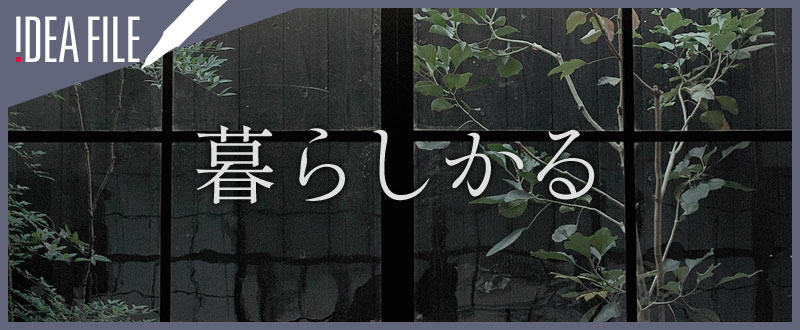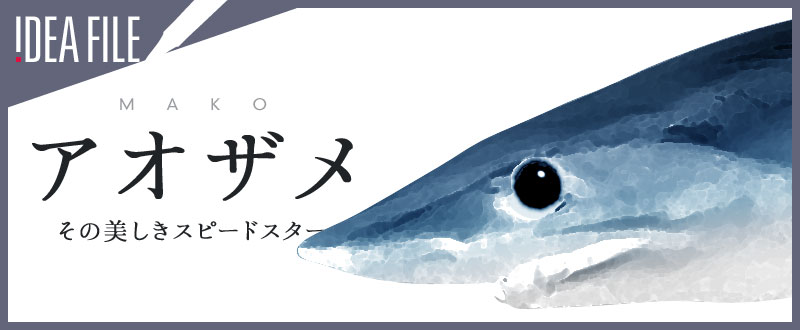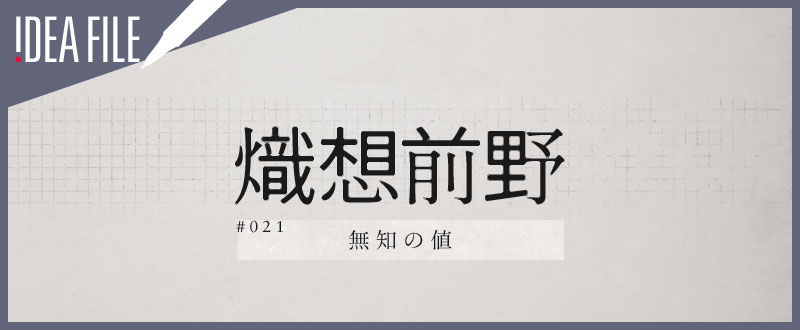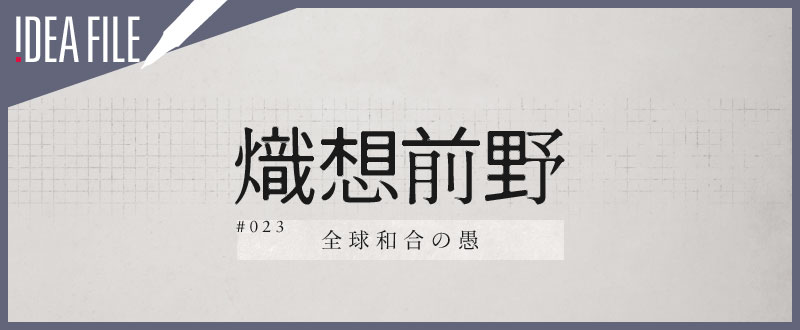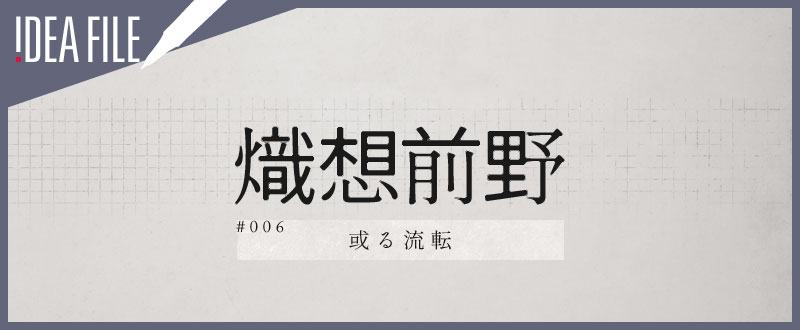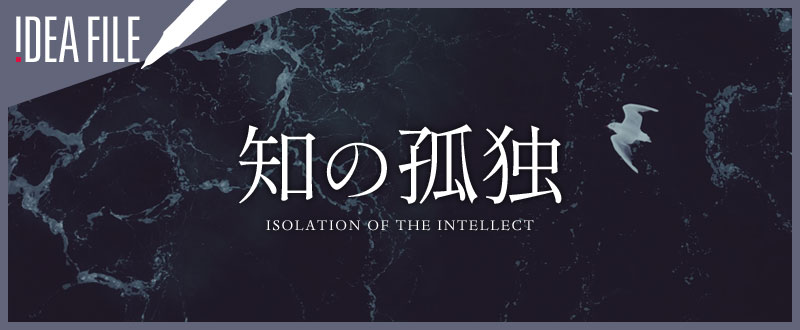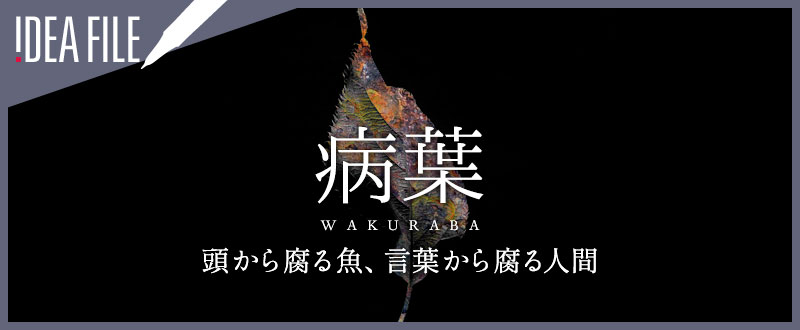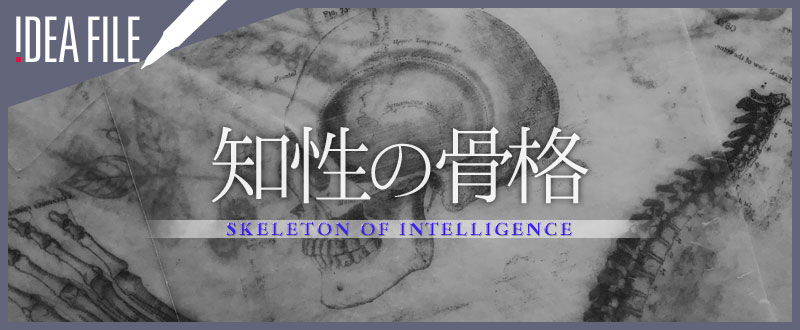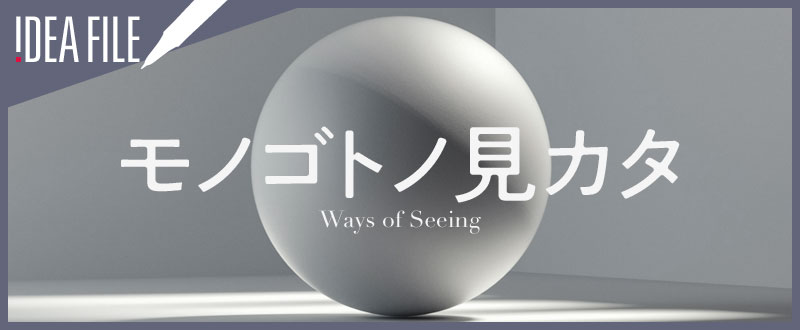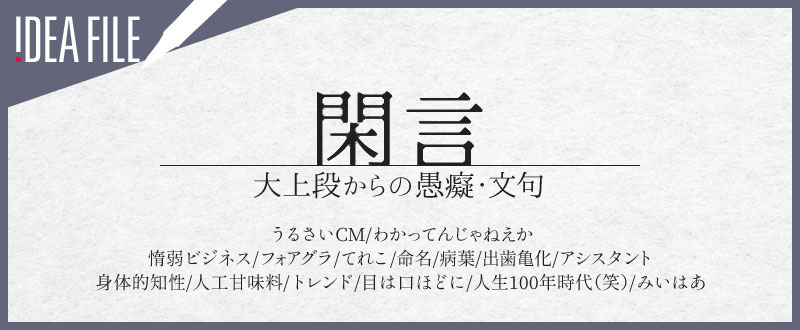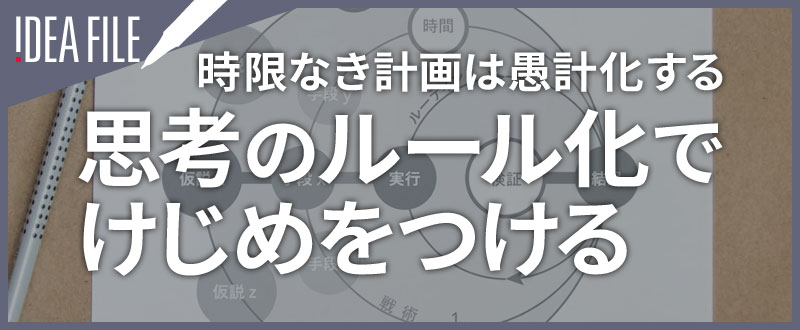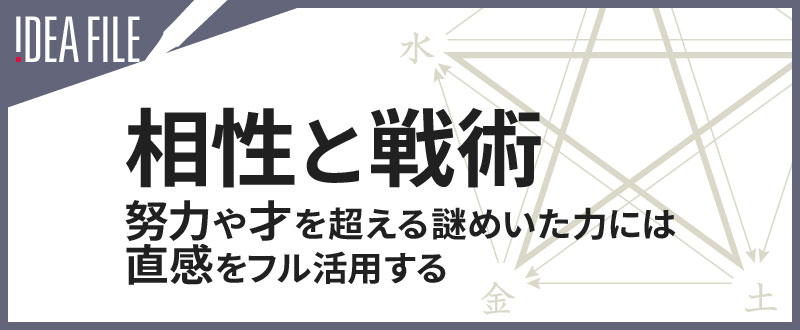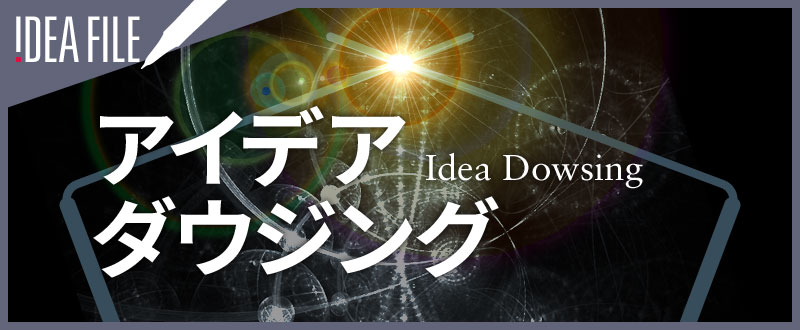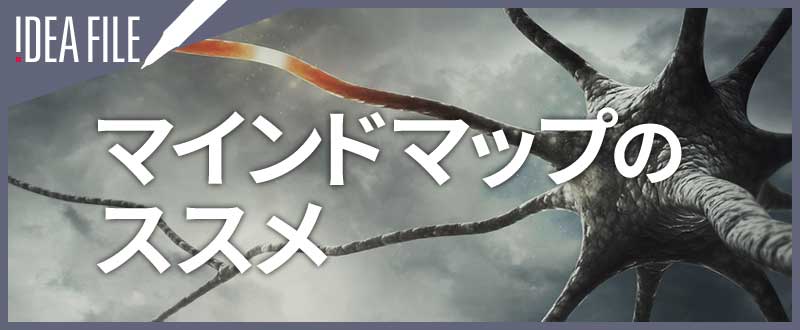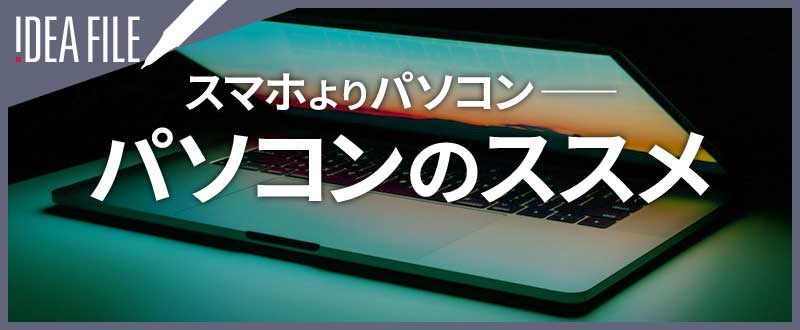貧すれば論ずる
貧すれば、声が小さくなりがちだ。これがいけない。貧者というのは、とかく犠牲を強いられるのが世の常。ならば貧しているものこそ、その言を鍛えねばならない。
貧すれば鈍する
国内の衰退ぶりを街歩き風に紹介するYouTubeチャンネルには、けっこうな視聴回数をかせいでいるものもある。「衰退」は今や日本のトレンドになっているようだ。全国に比して高齢化率も高い私の住んでいる地方も、零落れゆく景色の変化の早さのみが耳目をひきそうで、みじめなものなのだ。衰退途上国、現日本の、躁鬱病の鬱の光景。とはいえ、躁とてインバウンドだの何だの、引換えに煩苛になるのだから、静けさを好む私にとってはこちらのほうがましだ。
貧すれば鈍する
――
世に聞こえる諺なれど、こんな悲愴は、これぞ真理とあっさり受け入れてよいものではない。しかしまあ、貧する前から鈍していたものが、どさくさまぎれに己の愚鈍ぶりを貧のせいにしているのも見受ける。そういう輩はいつの世も捨て置くしかない。
こう言ってしまうと、貧とは何の関係もない鈍が実は世間の大方であった、という通り相場の話で終わってしまうので、拙文は実に迫り痴る危機にある賢明な御仁にのみ向いて書くことにする。
題して『貧すれば論ずる』。
貧すれば論ずる
貧すれば、声が小さくなりがちだ。カネ回りのわるさに自信をなくすもの、金策に駆けずり回り声を発している暇などないもの、いずれにせよ世間の表舞台では貧者の声は小さい。これがいけない。貧者というのは、とかく足蹴にされ、犠牲を強いられるのが世の常。ならば貧しているものこそ、その言★1を鍛えねばならない、饒舌にならねばならない。考えてもみてほしい。おとなしく黙ってそこに置かれた唐揚げと、食われてなるものかと灼熱の油をぺっぺと飛ばす唐揚げと、どちらが食えない(一筋縄ではいかない)か。おまけに言は貧者の大好きなロハ、無料。これを使わない手はない。
しかし、ここに落とし穴がある。鈍してしまってからでは、その鈍した口から、頭から放たれるいかなる言も言に似て非なるもの「汚言」となり、「汚言症」に陥る。「汚言症」とは、言中枢が鈍に侵され、言を制動できなくなる神経症のようなものだ。無意識的に汚い言葉を吐きつづけることしかできなくなる。SNSを見るといい。あの言空間のかなりの部分が、汚言の最終処分場と化している。ああなると逆効果、沈黙に勝る言が失われつづける。
SNSであつかわれるのは、一段落分程度(150字程度)の文字数だが、まっとうな弁を立てるにおいて、言の普請性というものを考えれば、少々、心許無い量だ。舌足らずなことばを不特定多数、開かれたネットの場に打ち上げれば、必然、最大級の群盲象を撫でる
現象が起こる。挙句の果てが、どちらの言者が勝っただの、敗けただの、きわめて浅薄皮相な尺度で結着するという阿鼻叫喚の言空間に堕する。これではせっかくの言が活きない。まあ、廃棄物のような言であるからこそ、最後は焼却(炎上)して幕引きにするというのだから律儀ではあるが。その点においては世間も捨てたものではない。
このような言の腐敗を止めるには、たとえば、SNSの投稿に必要な最低文字数を4,000字ぐらいにするといい。そうすると、その条件でそもアカウントをつくるものも篩にかけられ、すこしはましな言空間になるのではないか(広告収入を考えれば実現不可能だが)。
言を鍛えるとは、先ず以て言への崇敬からはじまる。言を無料だからと吐き散らすだけではただのでしかない。自然の水や空気も無料だが、生をもっとも支えるものであるように、言もおなじだ。言を敬い、幾星霜を経て維持、管理されてきた文化財であると認識し、醜く汚すことを目的とした使い方をしてはいけない。それは悪行為だ。己の生は、個人生をはるかに超えて在る言という偉観の一角に仮初、立たせていただいている、拝借している、そういう心持で良いぐらいなのだ。
言を用いて、世に、人に、己に問する、論ずるものであるべきだろう。ときに刺激的であるために、修辞の範囲かそれをいくらか逸脱してでも激しい言葉を使う必要にせまられることもあるかもしれない。しかし始終それでは人も、己すらも聞くに堪えない。
ところで、言を鍛えるにおいて誤解されがちだが、「読書」が必ずしも言を総合的に鍛えるわけではない。読書は言知識の増補、あるいは感覚的運動であって、言の中核である解釈に変容をもたらすほどの読書行為は稀だろう。凝り固まった、お定まりの解釈で幾千幾万の書物を読もうと、それはスクワットよりも楽な、何も鍛えぬ単純運動でしかないことを、読書家を自負するものを透して確認している。
どんな美味いものだろうと、食うだけでは美食家の域を出ない。おまけに美食が過ぎて体形(体系)がくずれるもの、一服盛られて(知性の)病に侵されるもの、いろいろある。言もただ渉猟すればよいというものではない。
言の真骨頂は自重(自らの精神の総観)で練られる解釈の運動と、そこから発せられる己の言にある。それも生活の言、ごく卑近な会話にまで滲透してはじめて、鍛えられた言というものをみることができる。
言も水や空気とおなじ、入れて、出すことで循環する。私は書物は好きだが読書家にはなりえない。読むだけの行為には飽いてしまう。むろん、吐きだす言が招く難もある。しかし、最終的に自身の内に難を仕舞うにも、己の言を駆使せざるをえない。これは読むより書く、論ずる行為にちかい。自己啓発本なるものを好む人を見れば顕著、論より証拠、読むだけの行為が如何なるものか、分かるというものだ。己が生の素直な衝動、内外発的な言の循環によって、言は生に親近するものなのだ。ロシュフコー★2の箴言集で解決するなら、それに越したことはないのだが。
貧してなお論ず。この先どれほど迫り痴る危機にあっても、私は黙りこくることはしない。黙ってむしり取られるだけの人生など、それこそほんとうに唐揚げの鶏である。
★1 言(げん)――ことば。ものをいうこと。
★2 フランソワ・ド・ラ・ロシュフコー――17世紀のフランスのモラリスト文学者。
貧すればnonする
non(ノン)はフランス語で「否」。貧するものは、そのあけすけな野において、絶えず向けられるバリ取りされていない現実の側面にたいし、「non」と言えなければならない。無駄な感情をまじえず、冷徹に「non」と。なぜならそれは現実の全体ではなく、あえてずさんに放り置かれた現実の側面、社会と人間精神の構造由来の皺寄せ、汚垢だからだ。物持と同じように自由・平等・博愛等の欺瞞に惚けるのなら、状況判断能力を喪失した、それはもはや偽善者、それはもはや貧困性認知症である。
貧するものこそ「non」と言う気構えが必要だ。それこそが貧しきものの幸い
、つまり知的に貧しいという人間の究極の貧しさ、不幸には達しないという幸いである。
貧すれば案ずる
「案ずる」、すなわち考え、工夫し、楽しむ機会を、貧は多くもたらしてくれる。富はその過程を富でもって手っ取り早くアウトソーシングしてしまえる分、時間的に富むのだが、知的には貧が必ずしも貧し、富が必ずしも富むというほど単純ではない。貧してよい大学に行けず、知においても後塵を拝す、という解釈も一理あるが、一流大学卒でも大金持ちでも丸出しの人間を何度も目にしてきたので、一概にそれをいうのは偏見というものだろう。事実に反する。
貧するものは論ずるうえで、インテリゲンチア★3に安易に追従すべきではない。なぜなら論というものは、あるいは鍛えられるべき論というものは、己が現実に耐えうる論でなければ空論にすぎない。彼らと貧富、あるいは階級を原因として現実を共にしていないのであれば、彼らの論は我らの空論と相成る仕儀なのだ。
にもかかわらず、たとえばポピュリズムに先鋭化したインテリゲンチアの思想、言説に「そうだ! そうだ!」といかにも乏しい言を発し、酔ってしまう。生まれてはじめて「きれいだよ」と言われて頬を赤らめる少女のように、危うい。目も当てられない。
「先生は頭が良すぎるというか、棲んでる世界が違うというか、理屈は分かるんですがね、理屈は理屈。如何せん、此処ではその論は華奢に過ぎる。実にはなりえんなあ」
現実に耐えるぶっとい論をもつものは、自分のことばをもつものでもある。論は己の手に、生に馴染むものでなければならない。言は剣、言は筆、言は箸である。
貧するものは案ずるものたれ――見えぬ先々に只々気遣うのではなく、考え工夫する創意と追従しない相異とを発揮すべきだ。それは孤独の精光であり、その光がまた論の裏打になりもするのである。
次回は『貧すれば豚汁』と題し、安くて美味い豚汁の作り方でも紹介しようと思う。
★3 インテリゲンチア――(もと帝政ロシアの西欧派自由主義者群の称)知識層、インテリ。