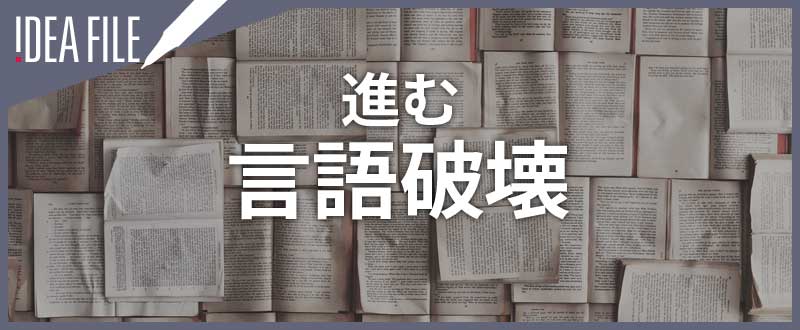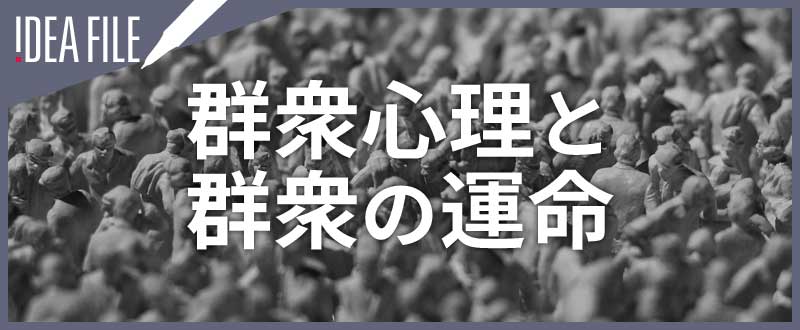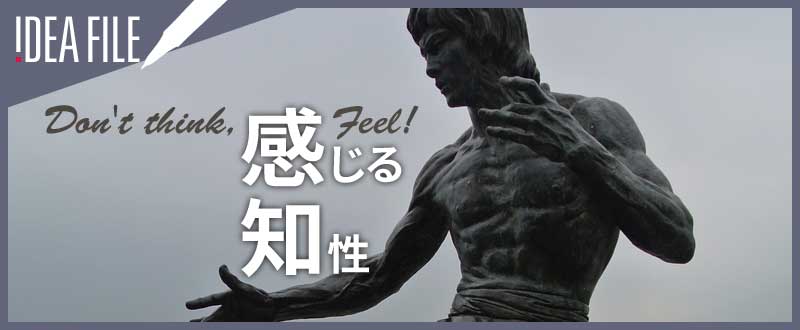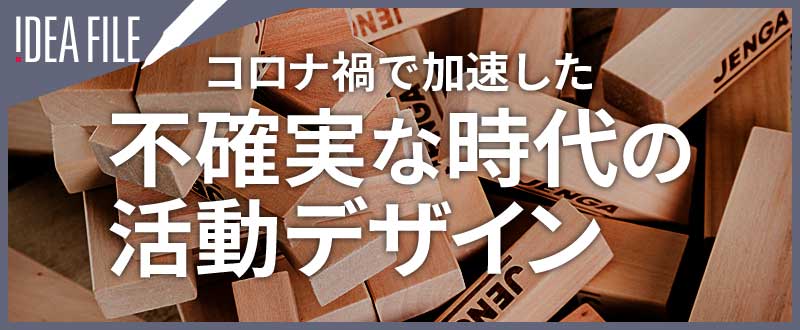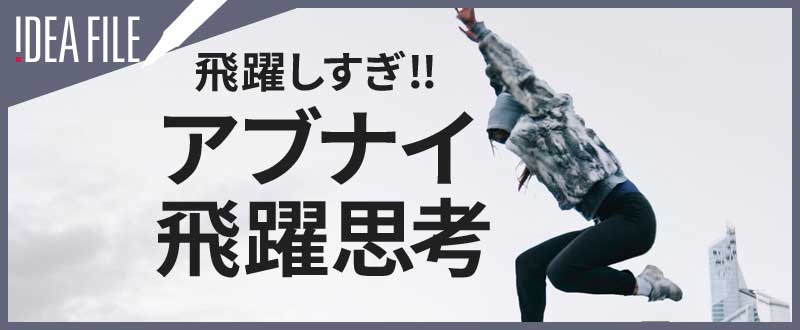死せる制度
群衆が英雄となりうる暗示は――技術が不可逆的なものである以上――もはや後世にあらわされることはないだろう。群衆はカロリー――コマーシャリズムを駆動させる熱量――だけを期待される。むろん、そのような体制にあっては価値であり、暗示は――実際には奴隷のような――その価値を巧みな修辞を用い擁護する。
ひとつの暗示、ひとつのきっかけを技術のパイプを通して群衆に垂らすだけで、それはたちまち「感染」する。巨大なイナーシャ(慣性、惰性)が轟々たる銅鑼の音のように知性の声をかき消す。それは群衆の知性のひ弱の証明である。どんな事件も――昨今のウイルスであれ――事の本質は「暗示」である。群衆の心象を統御してしまえば、それですべての頭は取れたも同然だ。
優勝劣敗から劣勝優敗へ価値逆転したような世に諦観を抱く個人もいることだろう。恣意的暗示にかけられ、死んだような群衆のネクロポリス(死人の都)にあって個人として生きる術がまったくないとは思わない。しかし、政治制度や社会制度が優勢のマスマンから劣勢のヒューマンに光を当て、救済する可能性はないに等しいだろう。それは問題の本質が常に制度にはないからである。
「議会」だろうと単に「群衆」である。次の引用は、国会議員ウージェーヌ・スピュレール(1835~1896)の言葉だ。「議会」について書かれたものを「群衆」についてのそれに置き換えるのに一字の修正も必要としない。
(前略)
彼等の冷静さは、その短気さと肩をならべ、その野蛮さは、その従順さと同程度である。(中略)彼等は、事物の因果関係というものを知らない。激昂しやすいが、意気阻喪するのも早い。恐慌に襲われやすく、気分の高低が常に度をすごし、決して必要な程度、適当な限界にとどまることがない。水よりも流動性に富んでいて、あらゆる色を映し、あらゆる形をとる、こういう人々のあいだに、どういう政治の基礎をすえつけることができるというのか?
――
ギュスターヴ・ル・ボン/櫻井成夫訳、『群衆心理』講談社学術文庫、1993年
制度が群衆の愚かさに歯止めをかけるのではない。制度とは、分布する群衆(党派、仲間、階級)のなかでもっとも優位にある群衆の、利益のための恣意的暗示を構造化・法規化したものにすぎない。制度が常に群衆に拝跪するのである。そのような優位な群衆同士の競合にあって、いわゆる心理学的群衆は上述のとおりすでに敗北している。彼ら群衆の時代はすでに終わっているのである。
まさにその証左として「イマだけカネだけジブンだけ」が敗北の群衆の骸に蛆のごとくわいているのである。

群衆の質が、議会の質である。議会は群衆の相似だ。愚かな群衆から析出された議会とその運動がデモクラシー(民主主義)に至るだろうなどと、非理である。むろん、それはオクロクラシー(衆愚政治)となり、毀誉褒貶する群衆に導かれた結果である。
緩慢な破局への時間稼ぎ
よく、何彼につけ「処方箋」を求める徒輩がいるが、世の中には不治の病などいくらでもあるのである。「群衆」もまた最初から、必然の衰滅を胚胎した運動であることを知らなければならない。理性や議論でどうにかなることのほうが稀なことだと知らなければならない。むしろ群衆の破局というものが一昼夜にしては来ないという歴史の大略に感謝すべきだろう。
そして現在、私(たち)は「緩慢な破局」への下り坂を、時間稼ぎをしながら歩いているにひとしい。
理想が次第に消滅するにつれて、種族は、その団結と統一と勢力との源泉となっていたものをますます失って行く。個人の人格と知能は、高まるかも知れないが、同時に、種族としての集団的な利己心は、極度に発達した個人的な利己心にとってかわられて、気力の減退と行動能力の低下とが、それに伴うのである。かつては一つの民族、一つの統一体、一つの全体を形づくっていたものが、遂には団結力のない個人の寄り合いと化してしまう。もっとも、この寄り合いは、伝統や制度によって、人為的になおしばらくのあいだは維持されはする。そのとき、人々は、それぞれの利害関係と願望とに応じて、たがいに分裂し、もはや自治の能力を失って、ごく些少な行為までも指導されることを求め、そして、国家が、吸収的な力をふるうのである。
――
ギュスターヴ・ル・ボン/櫻井成夫訳、『群衆心理』講談社学術文庫、1993年
ル・ボンの明察がいかに優れたものであるかを、彼の在世から約1世紀を経た現在、我々は現実として目の当たりにしている。空中分解をはじめた群衆の最期は、狡猾な個人が群衆への反目と閉塞した欲求とを掲げ、自らの共同体を貪り食らう。もとより知能というものをろくにもたない群衆の統御を国家に命じ、自分たちをより上手に支配してくれる支配者を待望する。かつて王から簒奪した神権を返上するのである。
世代を積み重ね作り上げた梯子を破壊し、文明と精神の段階の最初期まで落下し、野蛮に還る。そして、シュペングラーの見解を拝借すれば、文明の最期、野蛮な終末期には技術狂と狂信が流行する。新技術の小道具を握りしめ、鳴り物入りで登場した嚮導者だのトレンドだのに狂奔する。しかしその実、自発性や気力をことごとく流失させながら、物体としてのみ人間を象ったどこぞの亜粒子として消えていくのである。
一つの夢を追求しながら、野蛮状態から文明状態へ進み、ついで、この夢が効力を失うやいなや、衰えて死滅する。これが民族の生活が周期的にたどる過程なのである。
――
ギュスターヴ・ル・ボン/櫻井成夫訳、『群衆心理』講談社学術文庫、1993年

「末期的群衆社会」が、すなわち「逆無可有郷(ディストピア)」である。暗愚な支配層の奢恣の苗床は、群衆の愚かさにほかならない。
群衆の運命
生態系の覇者となり、天敵のいなくなった人間というものは、になって自らを無意識的に没落させ、抑制するのだろうか。
いずれにせよ、人は「群衆」でいる時、(個)人生を生きてはいない。仮に100年生きたとて、「群衆」の亜粒子でいた時間を引けば、人の精神的寿命は甚だしく短命化しているといえるだろう。マスメディアが煽る「人生100年時代」のなんと空虚なことか。
悪をなさず、求めるところは少なく。林中の象の如く独り歩め。
――
仏陀、『ダンマパダ - 第23章』
みなでおててつないでと呆け、群衆の一部に擬態しながらジブンさがしなど笑止千万である。群衆に擬態し隠蔽したおのれ自身を見失い、探している。ペーソスのきわみである。あげく、見つかることのないそのジブンをAIだのロボットだのに見つけてもらう情けない仕儀となる。
群衆人というものは、空気を吸って吐くことより読んでばかりいる。だから酸欠になって、ますます魯鈍になる。そうやって群衆人でいれば、最後、柩の中でも「Vサイン」をしつづける破目になるだろう。






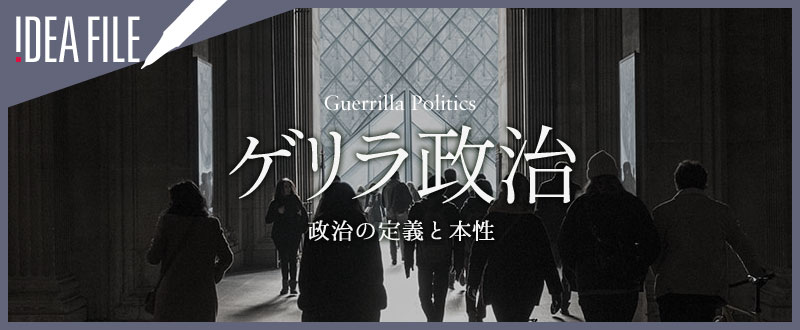

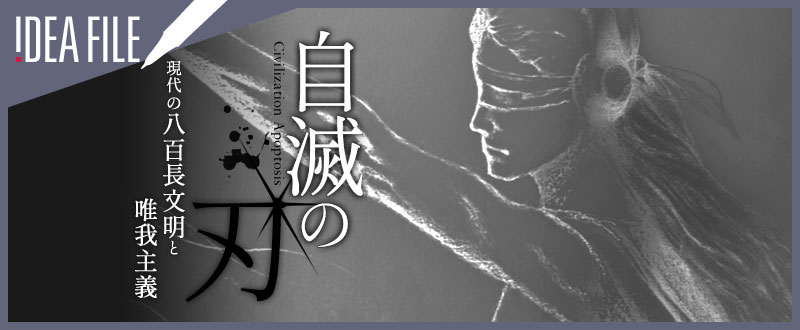

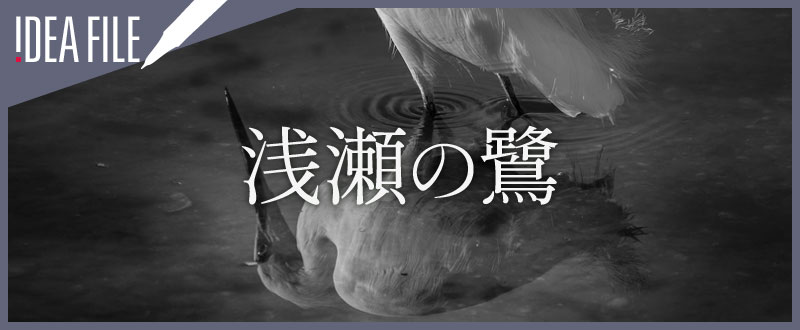

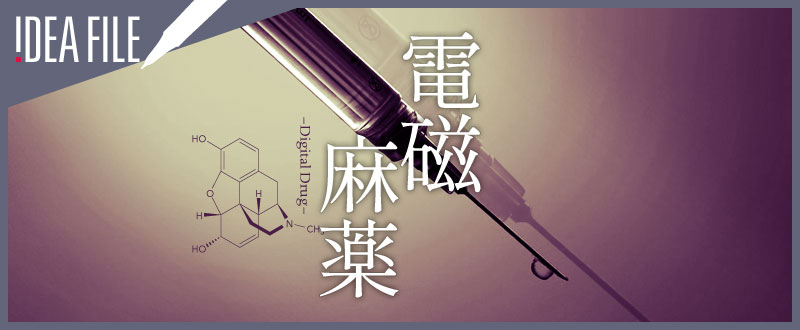

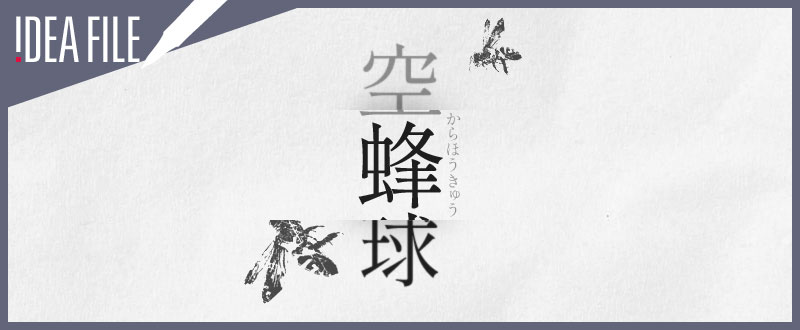





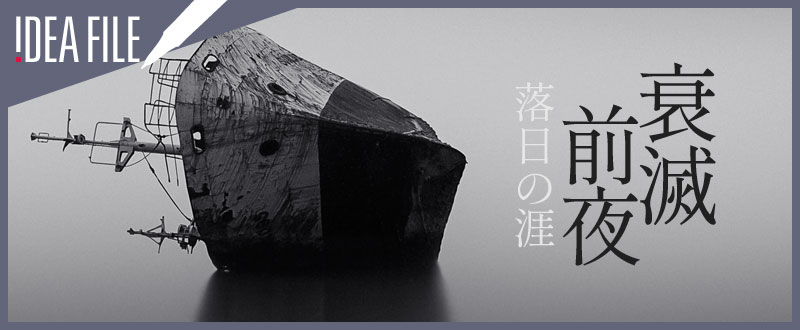

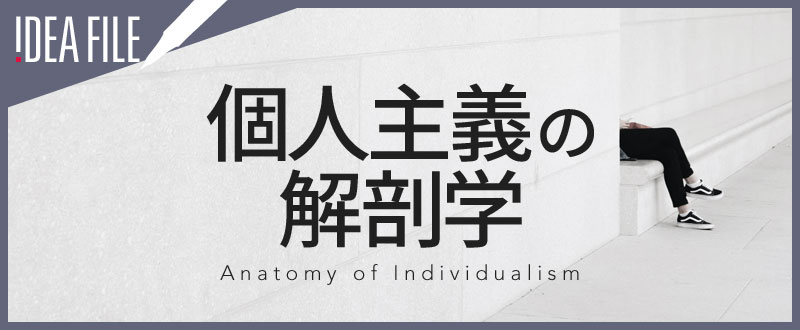
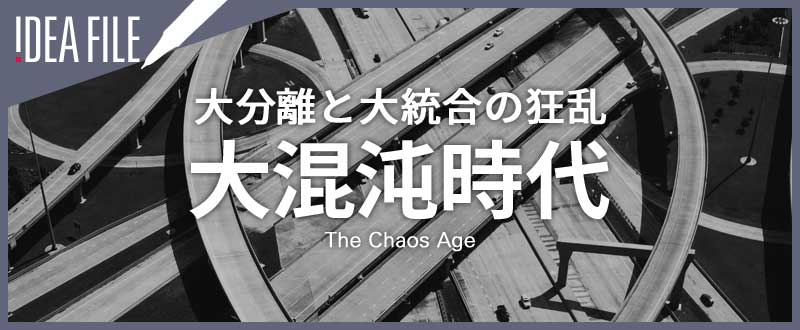
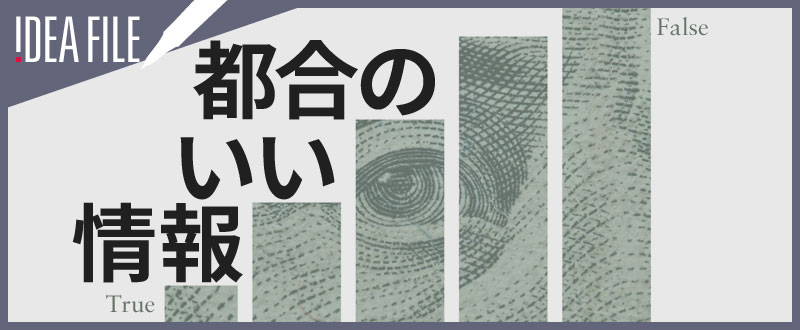

![統合失調症社会[国防編]](../article_0023/img/article_title_img.jpg)
![統合失調症社会[経済編]](../article_0022/img/article_title_img.jpg)