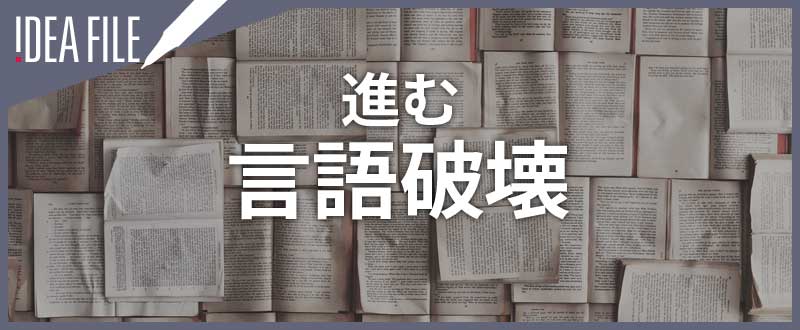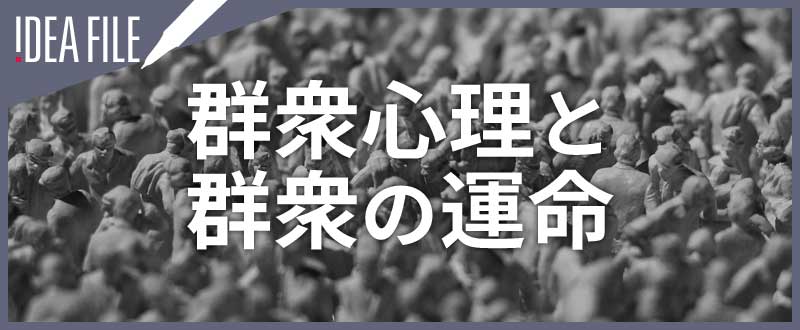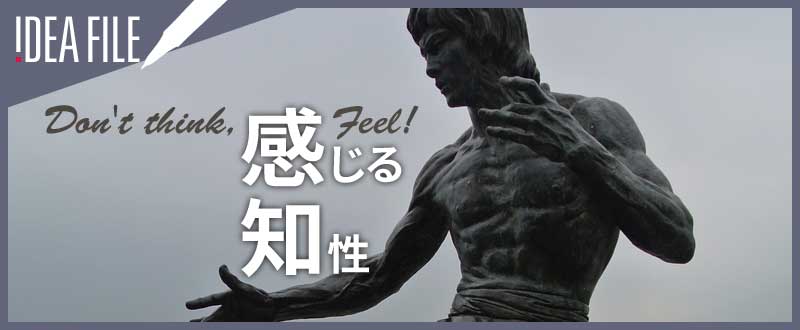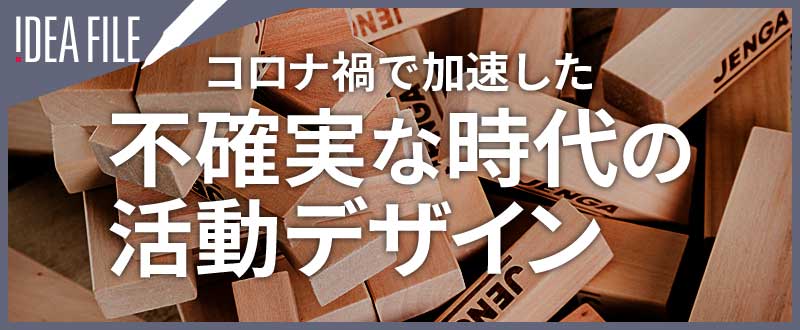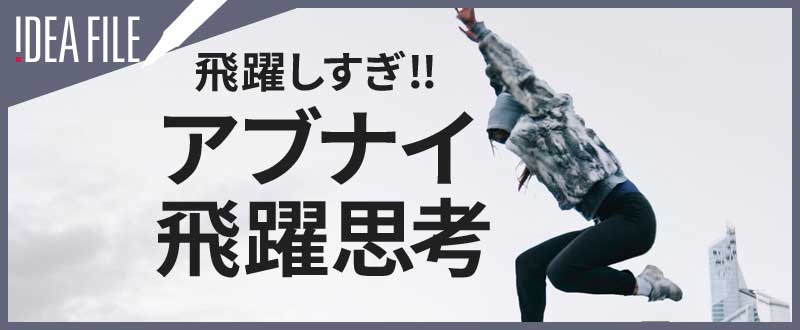ガラパゴス死史観
日本人の死史観と防災観
飲料水に非常食、災害への備えは完璧ですよ――したり顔でいう彼の似非防災観。人為的災害に疎いガラパゴス列島・日本のガラパゴス死史観、その危機的状況。
人為的災害に疎いガラパゴス列島、日本
災害への備えは完璧ですよ――したり顔でいう彼は、通信能力の大方を『LINE』にたよっている。これが日本人の一般的といってよいであろう似非防災観である(LINEの脆弱性★1についての言及は本論の任ではないので先に進む)。
「災害」を辞書で引けば、異常な自然現象や人為的原因によって、人間の社会生活や人命に受ける被害
とある。が、世人の「災害」の認識はおおむね「自然現象からの被害」であろう。
災害といえば「自然災害」、人為的災害は軍靴を鳴らしてやってくるものというような紋切型の単純解釈。「災害対策基本法」と「自衛隊法」で必要を満たしうる日本人の災害観。ゆえに「オレンジ計画★2」「超限戦★3」のような隠密性の人為的災害にたいし、きわめて脆弱である。平時における商品やサービスの選択において、その性能や利便性には目配りしても、資本体系や価値の潜伏性には想像すら及ばない。ガラパゴス諸島の野生動物たちが無防備といえるほど人間を恐れないように、「人為」に疎い。
災害への備えは完璧ですよ――彼の認識は、日本という国土の歴史から醸成された、ワラの家の子豚★4の認識である。
★1 ここでは過去、セキュリティー関連の脆弱性を指摘、公表され、比較的一般に認知されたものとして『LINE』を象徴的に取り上げた。そもデータ通信の危険性においては、なにも『LINE』にかぎったことではない。
★2 オレンジ計画――アメリカが日本を仮想敵国として想定し、日本との戦争に備えて策定した約40年に亘る軍事戦略。
★3 超限戦――中国人民解放軍の戦略研究から生まれた概念。戦争と非戦争、軍事と非軍事といったすべての境界と限度を超えた戦争、また戦争とは無関係に見える手段で政治的目的を達成する戦略。
★4 おとぎ話『三匹の子豚』より。
世紛争死史観、災害死史観
ここで
大石久和、『「国土学」が解き明かす日本の再興 ― 紛争死史観と災害死史観の視点から』海竜社、2021年
から「紛争死史観」と「災害死史観」という概念を拝借し、論を展開しよう。
ユーラシアやヨーロッパの歴史においては、人為的な「紛争」こそが危機的状況をもたらす最大級の要因であった。それにたいし、世界でも有数の被自然災害国である日本では、その国土的特徴から、危機的状況をもたらす最大級の要因は「自然災害」との認識が刻印づけられた。
このふたつの「史観」のちがいは、現在の文明社会においてもアーキタイプ(原型)として機能している。日本人のおもてなしの精神や海外迎謁の姿勢は、民族的な気立ての良さからくる、というのは皮相にすぎる解釈だろう。人為的な脅威にたいする警戒心の欠落が相対的にみて宥和と映っているだけだ。ガラパゴス諸島の野生動物たちが種として人懐こいのではなく、ヒトという種にたいする危惧が涵養される環境になかったのと同様に。
自然環境は短期間で変わるものではないが、社会環境は政治や経済、技術により常に変化の激湍にある。「紛争死史観」のものは、その観念を全球規模でたくましくすることで激動の世界に対応している。彼らは歴史的に紛争にともなう大虐殺や暴掠を経験することで、「人間の悪性」とそれにたいする「戦略観」とが基本的観念体系、あるいは知的慣習体系にしっかり据え付けられているのだ。
問題は「災害死史観」の日本人である。技術により四方を隔てる海はもはや無いにひとしい現在において尚、域際的問題において「話せば分かる」、「和を以て貴しとなす」などと「人間の善性」に訴え、否、ごまかしている。
敗戦後、明治に隆盛したリアリズムを反動的に解体した日本人は、先天性の「災害死史観」を盲目的に再起動し、「ガラパゴス死史観」に引きこもる。そして「人間の悪性」とそれにたいする「戦略観」の考究を放擲して80年、実物的に蚕食されている。このような結果を招いた原因は「人間の悪性」ではなく、旧態依然の観念硬直、「災害死史観」への偏執とそこからの無防備な態度にある。
人間はガラパゴスの野生動物ではない。環境にすべての原因を負わせることはできず、実践的原因の責を負う。雨に打たれて風邪をひくのは雨が降ったせいではなく、傘を持たなかったことが人間における原因であるように。
黄昏のガラパゴス
災害死史観の根底には、自然災害時の態度として「天災のときには日頃の諍いはともかく、みなで助け合う、助け合える」という情動神話があるのだろう。人間の多義性に人間の価値を見出す紛争死史観とは異なり、災害死史観は文明社会環境の激変という人為的、紛争的変化に人間観を動揺させる。
人為的災害には意図や計画があり、索り、仕掛けることで防災・減災が可能だ。ゆえに紛争死史観のものはそれらの能力を鋭敏にする。アメリカのCIA、イギリスのMI6、ロシアのSVR、イスラエルのMossad等はグローバルな舞台でパワフルに機能する。それにたいし、自然災害は事前に索ることができない、意図も計画もない事変である。日本がスパイ天国となった由縁は史観にあるのかもしれない。
ゆえに恒久的冷戦構造、すなわち紛争死史観スタンダードとなった近代、日本にとって「戦略観」がパラダイムシフトの要諦だった。しかし、系譜的存在の人間にとって、歴史の系統は重い。ヒューマニズムですらイデオロギーとしてではなく、環境由来の感覚に馴染むことで機能するような国民性に、突貫工事の「戦略観」は十全とはいかないのも無理はない。
そんな日本人に今さら災害死史観から紛争死史観に切り換えよといったところで、その刻印の深さを思えば詮無きこと。ガラパゴスの進化は一朝一夕には起きない。現在の日本の状況は、さながら「黄昏のガラパゴス」だ。「ガラパゴス諸島を実験的経済特区として開拓しよう」と意気込む人為的、紛争的変化にたいし、戦略も戦術も歴史的に奥手である。明治維新、戦後、そして令和の今はおなじ範型にある。
それら人為的災害にたいする動揺の態度の差異を今さらイデオロギーとして区分けし、対比し、騒ぎ立てたところで意味がない。リアリズムに則っていえば、戦後80年、徹底的に総括、研鑽すべきだった、紛争死史観スタンダードへの戦略と戦術を。日本の歴史的・社会科学的・環境生物学的・心理学的・文芸的その他種々の舞台で広汎にテーマ化すべきだったろう。だがもはや理も非もない。あらゆる事々を価値相対主義的に、無防備にまかせてきたのだ。
「災害死史観」という誤謬を無意識下深くに抱えつつ、この「静動の大紛争時代」を歩むしかない。高度経済成長期、つづくバブルという泡沫の夢に酔い痴れ、正気を失っていた時間と不摂生の付けを払う時が来たのだ。その道は困難を窮めるだろう。
駆り立てられ、性急にもとめる処方箋など、プラセボにもならぬ偽薬でおわる。あげく、身の振り方はAIに訊くか、流行りのインフルエンサーを猿真似するか、放縦に流れるかというありさま、つまり「頽廃」である。自ら招いた顛末なのだ。
黄昏のガラパゴス、ここへきて夜明けをもとめる声が上がりはじめた。が、黄昏と夜明けのあいだに横たわる闇夜を端折った夜明けなど、来るべくもない。
地震、火山、津波、台風にばかり気をとられていては背後ががら空きである。禍々しく陋劣、邪悪なもの――人間に時として浮かび上がるその輪郭をしっかと見極めないかぎり、全球規模になったこの文明で災を免れることはできない。地域ごと暗殺されることも、紛争史ではありえるのだ。






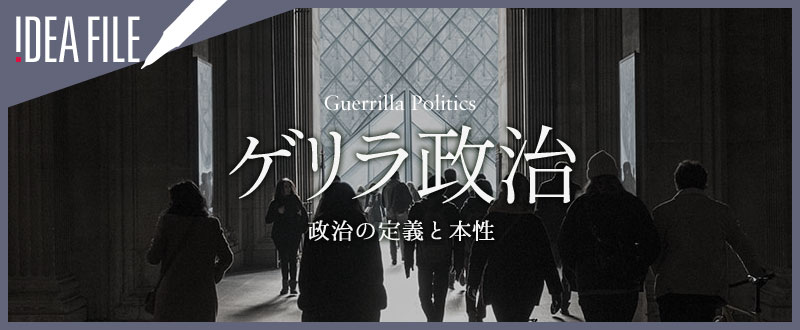

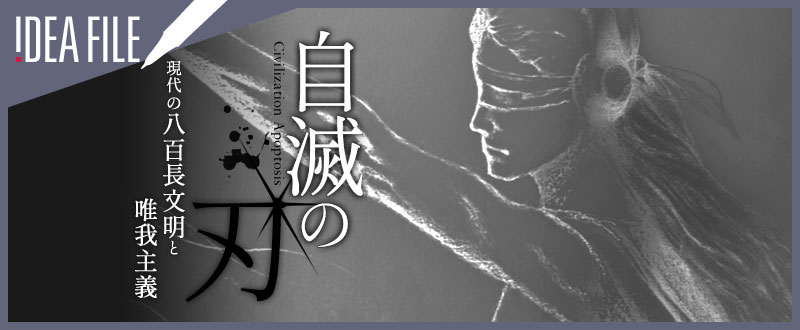

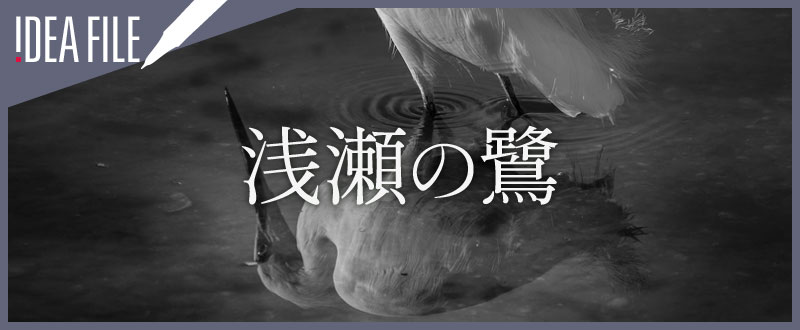

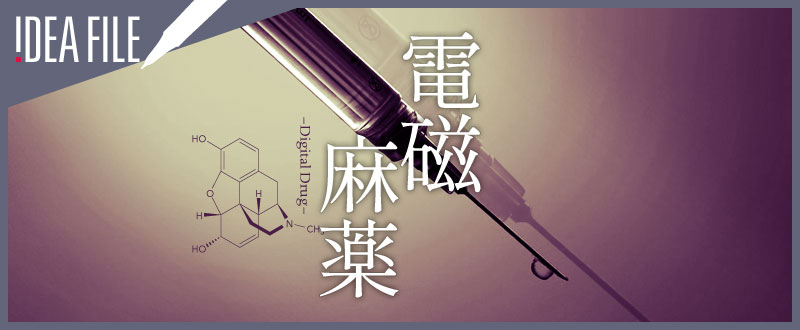

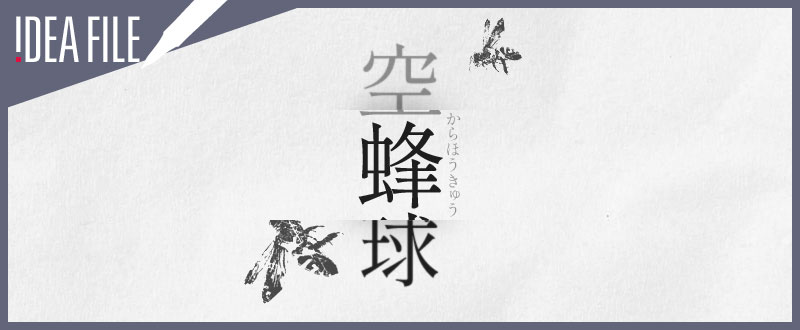





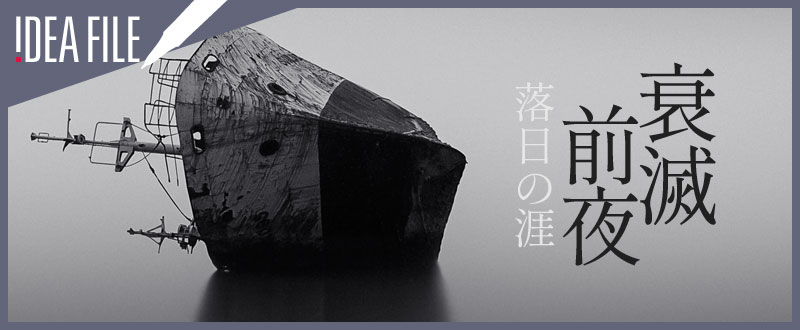

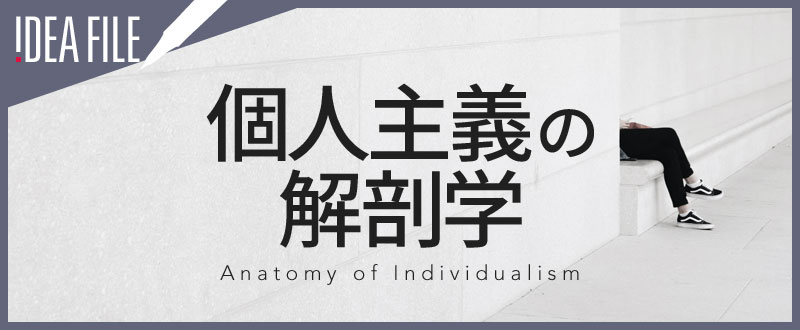
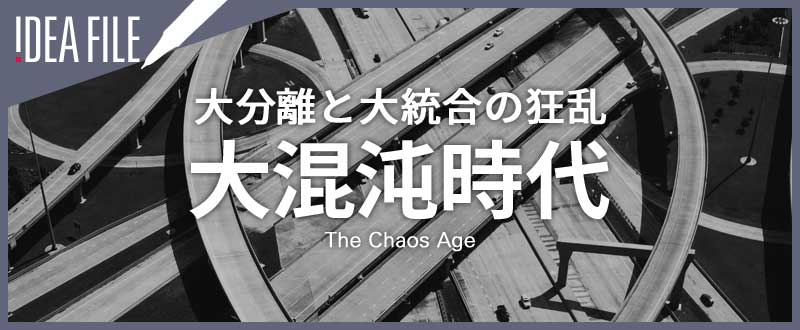
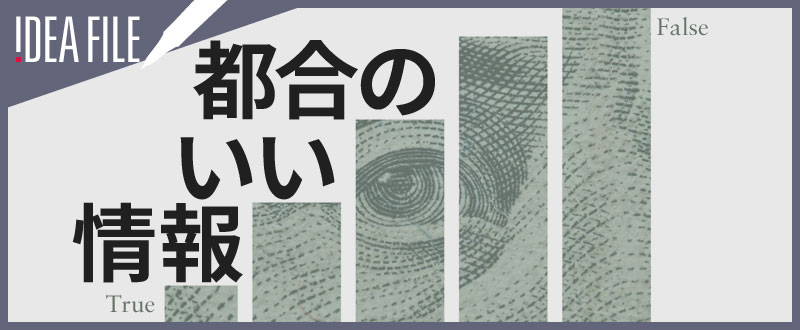

![統合失調症社会[国防編]](../article_0023/img/article_title_img.jpg)
![統合失調症社会[経済編]](../article_0022/img/article_title_img.jpg)