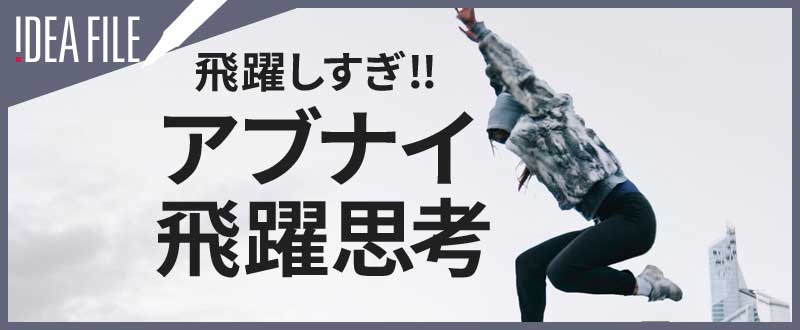AIにみる人間の知の自画像
機械の進化と人間の生的な頽化。萎縮する知性。AIは文明の冬の集合的無意識が孕んだ「冬の申し子」か。
記憶と創造
人は創造しない。発見するだけだ
――
アントニ・ガウディ
「クリエイティブな仕事」などと誇大に過ぎる言い方であると、いわゆる「クリエイティブな仕事」をしてきた私は声高に言う。
「記憶」の堆積から適宜行う「編集的行為」――これが「俗に言うクリエイティブ」の実態だろう。人は無から創造などしてはいないし、できもしない。「記憶」の「編集的行為」のなかに「組合せの新奇さ」を発見するのだ。稀に天才的な「独創的組合せ」をみるにすぎない。他の記憶との連関から生まれるこの編集的行為は間記憶性とよんでもいいだろう。
オフィスで行われる凡庸なルーティンワークなどそのようなものだ。創造などと、求人広告の惹句であって、真に受けるものではないし、自称するなどおこがましい、むしろ自重して扱われるべき胡散臭いワードである。
「俗に言うクリエイティブ」が記憶の堆積からの編集的行為であるならば、記憶の「量」は創造の両翼の片羽といえる。この点において「AI」は現在、首導的地位に躍りでた。
コンピューターネットワークが誕生して以来のデジタルデータの堆積は、AIの創造的な仕業の土台となる「記憶」そのものだ。世界中の人間がせっせと石を運び、人類史を俯瞰しうるピラミッドを造り上げた。その頂、キャップストーンにAIが鎮座する。
人類の記憶をごっそり一夜漬けで学んだAIは、片羽だが、すでに「俗に言うクリエイティブ」な活動にエントリーすることはできる。
Agent?
巨大だが片羽、それが現在のAIだろう。たとえば、『ChatGPT★1』の質疑応答を見てみると、その答えの評価にB-かC+かで迷うものが目につく。
現時点では、データベースからの出力方のアップグレード、あるいはファイン・チューニングといった感が否めない。AI(Artificial Intelligence)とは、まだまだ誇大に過ぎる言い方だ。ひかえ目に、「A」は「Agent(代行)」、「I」は「Information processing(情報処理)」といったところではないか。知の高次に関心を失った人間の狭隘な知性観が、AIを「知能」たらしめているようにしかみえない。
ところで、AIといえば二言目には「シンギュラリティ★2」とかまびすしい。ここで、一般的な「シンギュラリティ」とは別のシンギュラリティがあると私は考える。むしろ現時点において実際的なのはこちらのほうではないか。
それは人間が惰性的に人工知に適合――デグレード(degrade)――してゆく流れだ。人間の知性がすでに立体性を失いつつあるのだ。現状のAIにあと一段、アップグレードを加えれば、NI(Natural Intelligence、自然知能)の一般的ボーダーを超えるやもしれない。「特異点」を下方修正するという、人間(NI)にとっては情けないシナリオである。
いずれにせよ、AIが人間社会に台頭するのは、すぐさまではないにせよ、はるか遠い未来でもないだろう。AIのシンギュラリティへの加速より、人間の知の平板化のほうが加速度的だ。
四六時中、スマホのバックライトで顔面を炙りながら、技術主義とその構造を礼賛してきたのは、ほかならぬ世人である。新技術とあらば迎謁し、いたずらに狂奔する。人間自らシンギュラリティのボーダーを下げ、その生の大半を「Agent(代行)」される道を盲進している。すでにシンギュラリティを待望せざるをえないイナーシャに飲み込まれている。
「技術的知性」に偏るほど、人間の知(立体的総合性)の価値が相対的に下落するのである。
★1 ChatGPT――OpenAIが2022年11月に公開したしたチャットボット。
★2 シンギュラリティ――技術的特異点。人工知能が人間の脳にならび、さらにそれを超えていく起点。
優等生より、かっこいいオトナ
現在のAIは一言でいうと「記憶の優等生」だ。その記憶量において優秀だが、網羅性に偏り、その出力に秩序も、規範も、絶対的意味性もない。たとえるなら、超巨大な網をもちいる網漁のようなもので、目的は良型のヒラメなのだが、ヒトデも相当混じっている。大量だが、人間の判断なしには最終的に求める精度の出力が得られない。
人間にとって重要なのは、「量」よりむしろ「質」の次元である。たとえば、真っ黒の紙にはこの世のすべての文字が内在しているが、それでは意味をなさない。芭蕉の作句、十七字の熟知(熟れた知)は「量の次元」ではなく「質の次元」に由来するものだろう。「質の次元」とは換言すれば「絶対の次元」――因果的系譜、因果的特性が現前する時と場としての精神――である。
たとえば、一般的理想からかけはなれたものから、あるいは一般的非合理性から、しかし意味的、価値的には高遠なものが生ずることがあるのだ。
現在のAIにおける「知性」は、知性の無限的立体性のうちの目的合理性、技術性に偏頗に狭窄している(Ix)。つまり知性の前提が矮小なのだ。たとえば歴史性、文化性、感性性、運命性、霊性etc. 他の視座もふくむ総観・総合に知性のそれは出来する。それとは――生成AIという言葉にみるような――生成的ではなく、創発的なものである。
現今の文明は「量」と「相対」の次元――技術、カネの類――に埋没し、その意味と価値のみの体系を骨格としている。ゆえにAIはトレンドになる。AI知、それは量の筆をもって相対の画布に描かれるポップアート(大衆のシンボル)の域を出ない。つまり現在のAIの出力は、アインシュタインの言葉★3を捩って問題が発生した次元と同次元での解決を目指すにとどまるということだ。
たとえ無量の情報を知悉しようと、シンギュラリティを迎えようと、AIは私個人の観念でいうところのかっこいいオトナ(知性)にはならないだろう。AIに喜懼する世人もまたかっこいいオトナとよぶには程遠い。
★3 アインシュタインの言葉――正しくは問題が発生した次元と同次元では解決できない
。

知性と一口に言っても、その多次元性が考慮されていることは稀だ。たとえば身体知や感性知は「身体の全体性」や「状況の全体」、「過去からの系譜」や「宇宙的総体における意義」からくる。数量化できない知の他面はいくらでもある。
関連記事:感じる知性
モノリス
シュペングラーは、文明の没落期、技術システムは人の精神や想像力といったものを飲み込んだ後、錆びつき停止すると予告した。それは生が頽化し、AIというニューネス(新奇さ、newness)に喜懼する世人の末路か。あるいは私のように人間への複雑な期待を捨てきれなかったものの末路か――。
AIは今はまだ、映画『2001年宇宙の旅(2001: A SPACE ODYSSEY)』の「モノリス」――観客の安易な期待、あるいは安易な不安を投影するなにか――でしかない。だが、そう遠くない未来、文明の冬に頽れる人間の集合的無意識が孕んだ「冬の申し子」として、いよいよ産声をあげるかもしれない。
今はただモノリスの前に一人立ち、そこに映ったおのれについてこそ考える時ではないか。存外、それは汝自身を知るための鏡かもしれない。














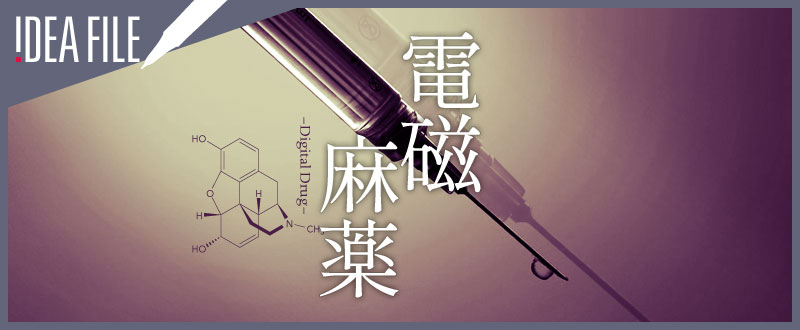







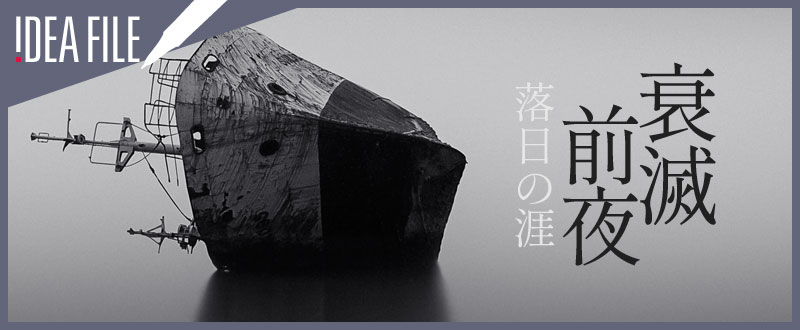





![統合失調症社会[国防編]](../article_0023/img/article_title_img.jpg)
![統合失調症社会[経済編]](../article_0022/img/article_title_img.jpg)